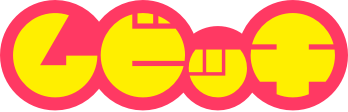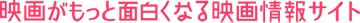『黒四角』の奥原浩志監督が、芥川賞作家・小川洋子の禁断の小説を、永瀬正敏と陸夏(ルシア)のダブル主演で映像化する日台合作映画『ホテルアイリス』が、2月18日より公開される。このほど、原作者・小川洋子と主演・永瀬正敏のインタビューが行われ、二人が作品について語った。
MC:小川さんの小説の映画化作品には、これまで『薬指の標本』と『博士の愛した数式』がありました。この2作と比べて、より大胆に翻案された『ホテルアイリス』。小川さんはご覧になり、どんな印象を持たれましたか?
小川:脚本をあらかじめ読んだときには、映画化するにあたっていろいろと手を加えたんだなと思いました。でも最終的に映画になった段階では、自分の小説とどこが違うとか、そんなことはもう全然気にならず。一つの完成された世界として、違和感なく観ることができましたね。
MC:合わせ鏡のモチーフが登場するなど、映画ならではの表現が加わっていましたね。
小川:小説の中に隠れていたものを、監督が見つけて拾い上げてくださったのかなという印象でした。
MC:小川さんは以前インタビューで、翻訳家というキャラクターについて「もう死しか残されていないようなお年寄りにしたかった」と話されていました。それを魅力的な永瀬さんが演じることで、見え方が違ってくる気もしたのですが。
小川:年齢は単なる数字でしかないんだなと思いました。たしかに小説で「老人」という言葉も使いましたが、この映画に登場するあの翻訳家も、ある意味では“老人”であり、何歳でもありうる。年齢という単純な枠組みを打ち破ったような存在感でしたよね。
MC:ある意味で、老人である。
小川:つまり、既に半分死んでいる。あるいは、実は“死者”だと言ってもいい。年齢を超越し、何歳であるかということに意味をなくした、死者。それを、永瀬さんが体現されたということだと思います。
永瀬:そうおっしゃっていただけてうれしいです。そこは最初にお話をいただいた時、僕も確認しました。老けメイクや特殊メイクをするのか?でもそれだとこの映画のためにならない気がして…。製作者さんサイドの意見は、準備稿の時点から「老人を下げ、マリの年齢を上げてやるつもりだ。年齢が近づいたときのケミストリーも見てみたい」と。それでわかりましたと。
MC:永瀬さんは翻訳家を演じるにあたり、あらかじめ原作小説は読まれましたか?
永瀬:読ませていただいて、すごく魅力を感じましたね。翻訳家だけではなく、主人公のマリや、あのホテルで働いている、盗み癖のあるおばさんとかも含めて。そういうさまざまな人たちの集合体として、面白い小説だなと思いました。
MC:それぞれのキャラクターに魅了されたということですね。
永瀬:ええ。あと、いつの時代の、どこの国の物語なのかわからない、浮遊しているような感覚も含めて魅力を感じたんだと思います。普段は現場に入ってからは、原作をあまり手に取らないんです。でも今回は原作を持ち歩き、何度も読み返しました。
MC:それはどうしてでしょうか?
永瀬:もちろん監督の書かれた脚本があってこそですが、映画の時間軸の中に、小説に描かれていること全部は収まり切らないですよね。となると、「ホテル・アイリス」から絶対に削ぎ落としちゃいけないところはどこなんだろうと思って。翌日撮る予定のシーンを原作で読み返しては、監督に自分の考えをお伝えすることもありました。
MC:特に原作が指針になったポイントは?
永瀬:いっぱいありますけどね。翻訳家が暮らしている孤島での、彼の重みのある立ち振る舞いだったり。そこからホテルアイリスのあるリゾート地へ渡ってきたときの、地に足がついていない感じだったり。
MC:リゾート地と孤島を行き来する中で、翻訳家の二面性をどう切り替えていくかにおいて、原作を参考にされたと。孤島に行くには、満潮のときは渡し舟が必要ですが、干潮のときは干潟に歩道が現れ、歩いて渡れるんですよね。
永瀬:翻訳家が孤島に歩いて帰ろうとして、途中で止まるシーンがあるんです。撮影している間に潮が満ちて、途中から島へ渡れなくなった。でもこれはチャンスなんじゃないかと、撮影したんです。とは言うもののこの場合、どっちの翻訳家として立っていればいいんだろうと少し考えてしまって。そういうときに、小川さんが書かれている一言一言を大事にしていました。
小川:とてもありがたい言葉です。
MC:劇中、台湾・金門島のロケーションが非常に魅力的でしたね。道にレンガが敷き詰められていたり、建物が石造りだったり。先ほど永瀬さんが言及された、まるでモン・サン=ミシェルのように、潮が引くと歩道が現れる孤島も、原作小説の雰囲気にぴったりでした。
小川:素晴らしいですよね。よくこんな場所があったなって。しかもホテルアイリスの建物が、実際も民宿だと聞いて、「ああ、小説家が想像して作ったものだと思っても、実はこの世界のどこかにそれは存在してるんだな」と、ちょっと面白い錯覚に陥りました。
永瀬:ロケーションは役を演じる上で、いわば共演者の一人みたいなもの。非常に大切なんです。小川さんが今おっしゃったように、金門島は原作のイメージにスッとつながって、監督はよく探されたなと思いました。
MC:ロケーションという意味では、お二人はそれぞれ、どんな部分が印象に残りましたか?
永瀬:やはり潮が引くと現れる歩道ですね。たしか、朝方と夕方の一瞬しか歩いて渡れなかったんじゃなかったかな。限られた時間の中でどう撮影するか?スタッフの皆さんは大変だったでしょうが、様々なアイデアを出し合って撮影できた。この歩道のあり方が作品にぴったりだと思いました。
小川:私は、小説では大きい遊覧船で行き来するイメージだったんですが、映画では渡し舟風になっていて。その舟を漕ぐ売店のおじさんの佇まいが、すごくよかったんですよね。海辺にある売店や、売っているものの感じとかも。自分の小説にも、この人を登場させたかったと思ったほどでした。
MC:台湾人俳優、リー・カンションさんが意味ありげな視線で演じていましたね。
小川:マリと翻訳家は切実な状況にあります。おじさんはこの二人とは全く無関係の立場にいながら、彼らをあちらへ渡すという、実はとてつもなく重要な役目を果たしていて。そのことに気づいていないのか、それとも気づいていないふりをしているのか、あの不機嫌で、無責任な感じが印象的でした。
MC:この映画はバイリンガルで、劇中、日本人のキャストが話すのは日本語、台湾人のキャストが話すのは北京語です。でも台湾人の陸夏さんが演じるマリだけが、母語の北京語と、母語でない日本語の両方を話します。
小川:それは、この映画の大事な要素の一つだと思います。マリと翻訳家がやりとりし合うのは、“言葉にならないもの”です。なぜ言語が混じり合っているのか、最初は不自然に思われる方もいるかわかりません。でも言語や言葉の意味なんて、この二人にはあまり関係ないことが、映画を観ていくうちにだんだんわかってくるんですよね。二人はまるで小鳥がさえずり合うように、“意味じゃないもの”をやりとりしている。あるいは、肉体と肉体をやりとりしている。そういう関係性を一つ、言語の問題が象徴していると思います。
MC:小川さんが過去のインタビューでおっしゃってきた「文学は、言葉にできないことを言葉にしようとすること」という考え方とも少しリンクしますね。
小川:人によってはこの映画を観て、「ちゃんと言葉でわかるように説明してくれ」という気持ちになるかもしれません。でも実は、言葉にならない部分に重要な真実が隠れている。そこまで行き着いてほしいなと思います。
MC:陸夏さんは今回が映画初出演。日本語のセリフや、ヌードのシーンがある中、堂々と演じてらっしゃいました。
永瀬:肝が座っていましたね、最初から。今回の現場には台湾人のスタッフも、若くてしっかりした女性が多かったから、安心できる現場だったんじゃないかなと思います。
MC:肝が据わっていると、どういうところから感じましたか?
永瀬:マリが翻訳家と関係を持つシーンの撮影のとき、陸夏は待ち時間もずっとあの部屋の中に、体に何か一枚羽織っている程度のままでいたんですよね。そうすることで何かを自分の中に入れて、マリに変わろうとしていたのかな。初めての映画ということもあり、とにかくなんでも吸収しようと一生懸命準備していた姿をよく覚えています。
MC:態度を見ているだけで、本気度が伝わってきたと。
永瀬:かなり不安もあっただろうし、いろいろ思い悩んだと思うんです。そういうときは、みんなで夜ご飯を食べに行って。(撮影はコロナ禍前の2018年で)まだそういうことができる時期だったので。「みんなで明日も頑張りましょうー!」なんてふざけて言い合ったりしました。
MC:映画はシリアスですが、現場は和気藹々とした感じだったんですね。そういえばマリの父親を演じたマー・ジーシアンさんは、永瀬さん主演の2014年の台湾映画『KANO 1931海の向こうの甲子園』の監督でしたね。
永瀬:出演してくれて嬉しかったですね。元々素晴らしい俳優さんでもあるので、俳優同士で共演できたのも嬉しかったです。実はサプライズで『KANO』のスタッフが10人くらい、金門島で僕が泊まっていたホテルまで来てくれたんですよ。きっとマーさんが「永瀬が台湾に来てるよ」って言ってくれたんだと思うんですけど。びっくりして、でもうれしくて、廊下で記念写真を撮ったりしました。
MC:ツァイ・ミンリャン監督も現場にいらしたそうですね。
永瀬:ツァイさんとも沢山お話ができて楽しかったです。以前国際映画祭等でちらっとお会いしたことはありましたが、あまりお話できていなかっいたので。撮影が終わるとホテルのテラスで毎日マーさんと3人で深い時間まで話ししてましたね。
MC:小川さんから永瀬さんへ、何か映画のことで聞きたいことがあればぜひ。
小川:あの海辺のシーンの足は、やっぱり永瀬さんの足なんですか?
永瀬:それは…。
小川:あ、言わない方がいい?(笑)
永瀬は取材が終わると、ボロボロになった文庫本を取り出し、小川にサインを求めていた。初対面ながら、終始お互いをリスペクトし合った様子だった。




『ホテルアイリス』
2022年2月18日(金)より、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ渋谷、シネ・リーブル池袋ほか全国公開
監督・脚本:奥原浩志
原作:小川洋子「ホテル・アイリス」
出演:永瀬正敏 陸夏(ルシア) 菜葉菜 寛一郎 マー・ジーシャン パオ・ジョンファン 大島葉子 リー・カンション
配給:リアリーライクフィルムズ 長谷工作室
【ストーリー】 寂れた海沿いのリゾート地…そこで日本人の母親が経営するホテル・アイリスを手伝っているマリ(陸夏)は、ある日階上で響き渡る女の悲鳴を聞く。赤いキャミソールのその女は、男の罵声と暴力から逃れようと取り乱している。マリは茫然自失で、ただならぬその状況を静観している。一方で、男の振る舞いに激しく惹かれているもう一人の自分がいて、無意識の中の何かが覚醒していくことにも気づき始めていた。男は、ロシア文学の翻訳家で、小舟で少し渡った孤島で独りで暮らしているという。住人たちは、彼が過去に起きた殺人事件の真犯人ではないかと、まことしやかに噂した。またマリも、台湾人の父親が不慮の事故死を遂げた過去を持ち、そのオブセッションから立ち直れずにいた。男とマリの奇妙な巡り合わせは、二人の人生を大きく揺さぶり始める。
© 長谷工作室