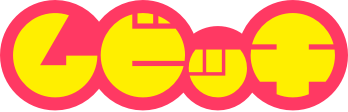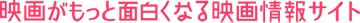第70回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールに輝き、本年度アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた映画『ザ・スクエア 思いやりの聖域』が4月28日より公開となる。それに先立ち、4月15日に代官山 蔦屋書店にてトークイベントが行われ、東京国立近代美術館研究員の保坂健二朗、精神科医の名越康文、美術家・ドラァグクイーンのヴィヴィアン佐藤が登壇した。
 ▲(左から)名越康文、保坂健二朗、ヴィヴィアン佐藤
▲(左から)名越康文、保坂健二朗、ヴィヴィアン佐藤
現代アート美術館のキュレーターが、盗まれた財布とスマートフォンを見つけるために“ある行動”を取ったことで予想外の事態に巻き込まれていく様を描く本作。映画の感想を尋ねられると、名越は「僕は菊地成孔さんとよく対談をする機会があるんですが、彼に“『ザ・スクエア』観た?面白かったですよ”って言われたんです。伏し目がちに笑っていて、意味ありげでね、ずっと気になっていた。観て、その意味が分かりました(笑)」と一言。東京国立近代美術館に18年間学芸員として勤めている保坂は「この映画はスウェーデンの美術館が舞台で、そこのキュレーターが主人公ですが、映画を観ていると自分と同じ職業でも外国の美術館は色々と違うことがあるなと感じました。こんなパーティがあるんだとか、こんなにキュレーターの部屋って大きいんだぁ、いいなぁ、とか(笑)。ガラ・パーティ(※美術館が資金集めのために開くパーティ)だって、日本だと森美術館ぐらいしかやってないだろうと思うんですが、やっぱり普通にあるんだなぁって」と、長年キュレーターを経験してきたからこその感想を述べた。ヴィヴィアンは「前作の『フレンチアルプスで起きたこと』も大好きで、映像が大変美しい。無駄な動きのない、意味のある空間や奥行きを感じるつくりのカメラワークで、それに反してどろどろした人間の内面、情念を描く。その対比が面白い。また、“これがアートです”と断言できるものは存在するのだろうか、ということを考えさせられますよね」と本作のアートという題材の扱い方にも言及した。
続けて、保坂が「アートって便利に使われがちな言葉なんですよね」と指摘。「よく分からなければ、“アートだね~”って言っておけば済んでしまう、みたいな(笑)。現代美術のキュレーターというのは、そういう作品を全世界から美術館へと集める仕事。厳密に言うと、キュレーターという言葉の語源は、ルナティックス―いわゆる心の病を患う人々を塔に入れて、それを護る人をキュレーターと呼んでいたそうです。人や物を守護する管理人の役割を持っていた人の呼称が、ただ管理するのではなく、人にそれを“見せる”ことになり、展覧会を構成する人へと意味が変わっていった。今では、新しい意味を生み出す人のような認識になっている。『ザ・スクエア 思いやりの聖域』では、主人公のキュレーター、クリスティアンが記者発表の中で作品の説明をしていましたが、本来、それはアーティストがすべきこと。今、世界的にキュレーターがアーティスト化していると言われていて、この映画はそれを象徴していると感じました」と語った。それを受けて、名越は「今、保坂さんからキュレーターの語源を聞いてゾクッとしました。僕の専門でもある精神医療の話になりますが、精神病院というのは19世紀頃には監獄と変わらない状況だったんです。酷いところでは、彼らを見せものにしていたという、実際にそういう記録が残っているんです。キュレーターの意味が、精神を病んだ人を護る人から“見せる”人へと意味が変わったというのが、精神医療の歴史ともどこかリンクするものがあるように思えてしまいました」と驚いた様子だった。
さらに話題は、本作の鍵を握るエピソードの1つでもある、美術館が作成した宣伝動画の炎上問題についても及んだ。ヴィヴィアンが「“これくらいやった方が盛り上がるんじゃないの”って言って意図的に狙って動画を作る、あの炎上商法の場面もすごいですよね」と唸ると、保坂が「広報チームに美術館だけじゃなくて外部の人間も入っているというのが、日本では通常ないことですね」と日本の美術業界にも話を拡大。「いま世界的に言われているのは、どこで検閲を入れるのかということ。表現の自由の問題ですね。表現の自由を広報に対しても適用するなら、『ザ・スクエア 思いやりの聖域』に出てくるあの動画はアリということになる。でも、まぁ、日本ではあれは不可能でしょう。日本ではここ最近忖度が問題になっていますが、内部検閲がほかの国に比べて強いです」と答え、ヴィヴィアンも「アートに限らず、映画とかもそうですけど、万人向けするものが多い気がしますね、日本は」とコメントした。
本作で、炎上問題のみならず劇中発生するあらゆるハプニングをまとめて被ることになるのは、敏腕キュレーターの主人公・クリスティアン。彼について、名越は「極めて人間的な人ですね。人間は例外なく神経症的であるということを喝破している。そういう意味では、典型的な“人間”。絶えず怯えていて、ある程度知的で、自分が本質からずれたことをやっていると分かっているからこそ、それに何とか自分なりに理屈をつけようとしてワーカホリックになっていく。カメラに映っているクリスティアンの9割に不安が浮かんでますからね(笑)」と述べ、ヴィヴィアンも「これでもかっていうほど、彼に災難が降りかかりますよね。まるで、小さなコントの連続みたいな。この人が全部引き受けなくてもいいのでは、と思っちゃうんですが、逆に言うと、クリスティアンというキャラクターの中には大勢の人物が入っているんでしょうね。だからこそ感情移入しやすい。私たちの代表なんです。彼は、私たちの相対」と考察した。
最後に、3人が再びそれぞれ映画への感想を総括。保坂は「今の時代、アートにおける美術館の重要性は段々変化してきている。アートの中心は、ビエンナーレとかアートフェア。そういう催しの中心って、どんどん変わるんですよね。例えば、アート・バーゼルは前回は香港だったけど、次はスイスのバーゼルです。そうした状況の中で、美術館は一歩引いた状況になっている。だから存在感を示すため、この映画の美術館は、そこに打って出て、炎上したというところでしょうか(笑)。本当に色んな問題がてんこ盛りの映画です」と美術業界を肌で知る保坂ならではの言葉で締められた。名越は「僕はこの映画を観て、キューブリックを思い浮かべたんです。普段は抑圧している人間の暴力性がヒリヒリと浮かび上がっていくという意味では、『時計じかけのオレンジ』や『2001年宇宙の旅』を連想した。キューブリックは影の入れ方や色の使い方全て丹念で、そういう意味ではノイローゼの極地みたいな人。追い詰め型というか。『ザ・スクエア 思いやりの聖域』も手法は違うがそのタイプ。ストレスフルでもあるが、観終わった後に必ず何かが変わる映画ですよね」と世界の見え方が変わる映画として本作を推薦。ヴィヴィアンは「ハプニングが起きても、周りの人が傍観するだけで誰も助けようとしない“傍観者効果”っていうのも重要なテーマの1つとして描かれているじゃないですか。そういった点にも注意して観てみるのもいいと思います!私も違った意味で傍観者効果を感じることがありますからね。授業で“質問ありますか?”って聞いても手が挙がらないことが多いけど、質問がないって言うのは、そこにいなかったっていうのと同じですからね!」と喝。まだまだ3人の話が尽きない中、トークは幕を閉じた。

『ザ・スクエア 思いやりの聖域』
4月28日(土)よりヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamura ル・シネマ、立川シネマシティ他全国順次公開
監督・脚本:リューベン・オストルンド
出演:クレス・バング エリザベス・モス ドミニク・ウェスト テリー・ノタリー
配給:トランスフォーマー
【ストーリー】 クリスティアンは現代美術館のキュレーター。洗練されたファッションに身を包み、バツイチだが2人の愛すべき娘を持ち、そのキャリアは順風満帆のように見えた。彼は次の展覧会で「ザ・スクエア」という地面に正方形を描いた作品を展示とすると発表する。その中では「すべての人が公平に扱われる」という「思いやりの聖域」をテーマにした参加型アートで、現代社会に蔓延るエゴイズムや貧富の格差に一石を投じる狙いがあった。だが、ある日、携帯と財布を盗まれたことに対して彼がとった行動は、同僚や友人、果ては子供たちをも裏切るものだった―。
© 2017 Plattform Produktion AB / Société Parisienne de Production / Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office ApS