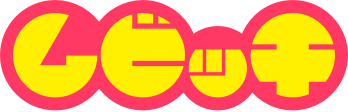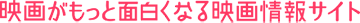日本人として初めてヴェネツィア・ビエンナーレ&ヴェネツィア国際映画祭の全額出資を得た長谷井宏紀監督がフィリピンを舞台に撮影し、世界中の映画祭で高い評価を得た話題作『ブランカとギター弾き』がシネスイッチ銀座ほかにて7月29日(土)より全国順次ロードショー。本作のトークイベントが7月24日、東京・港区のユニセフハウスにて行われ、フォトジャーナリスト安田菜津紀、監督の長谷井宏紀が登壇した。
本作の舞台はカラフルでエネルギーに溢れたマニラのスラム。YouTubeの歌姫として国内外で人気を集めていたブランカ役のサイデル・ガブデロは演技初挑戦ながら、美しい歌声と演技力で観る者を強く惹きつける。彼女に生きる術を教える盲目のギター弾きには、生涯を通して実際にフィリピンの街角で流しの音楽家として活躍していたピーター・ミラリ。その他、出演者のほとんどは路上でキャスティングされている。そして劇中、演奏されるスペインをルーツにした素朴で温かいフィリピン民謡「カリノサ」は必聴。母親を買うことを思いついた孤児の少女ブランカと、盲目のギター弾きの“幸せを探す旅”。本作はどんな人生にも勇気を持って、立ち向かう価値があることを教えてくれる、心温まる感動作となっている。
MCの呼びかけで、拍手喝采の中、本作の監督・脚本を担当した長谷井監督と世界中で貧困の問題を取材してきたフォトジャーナリストの安田菜津紀が登場。「映画を観ていただいてありがとうございました」と監督、「まだ皆さんの心は映画の中にあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します」と安田が一言挨拶。最初に、映画を観たばかりの安田にMCから感想を求められると、「長谷井監督ほど長い時間を過ごしていたわけではないのですが、マニラを旅してきた自分として、懐かしいな、という気持ちが湧いてきました。フィリピンに行ったことがあることを抜きにしても、人のエネルギーが交差していく、部分は皆さんが触れた所だと思います」と実体験を踏まえ感想を語った。
安田からフィリピンとの縁を聞かれた長谷井は「28歳くらいの時に友人が撮影したスモーキー・マウンテンの写真を見て、少しヘビーな写真だったのですが、行ってみたいなという気持ちになりました。実際行ってみて、危ないと感じたこともありますが、子どもたちの輝いている力を感じた。彼らはプライドを持って仕事していて、遊んでいる。その姿を見て衝撃を受けました。自分が社会的にどこに属しているかを気にしない、たくましく走り抜ける子供たちを見て、なんて美しくて自由なんだと思い、そこからよくフィリピンに行くようになりました」と振り返った。安田がその話を受けて、「この映画は北風と太陽のような話だな、と思いました。北風と太陽が旅人のコートを脱がせようとするけれど、結局旅人は太陽の暖かさを受けてコートを脱ぐ。人がコートを脱いでくれるには太陽の熱のような暖かさが必要で、この映画からもその暖かい熱を感じることができました」とイソップ童話の名作「北風と太陽」を引き合いに出してコメント。長谷井もその話を受け、「その暖かい入り口から、自分たちの社会だったり暮らしを感じて欲しいな、と思います」と話した。
フィリピンでの撮影中の様子を安田から質問されると、「街を歩いていると、至る所から僕の名前が、コーキ、コーキって呼ばれる。そこで食べ物が出てきて、あったかく迎えてくれる人たちばかり。フィリピンってすごいなって思うのが、一年前に5分しか会ってない人たちが、また覚えて声をかけてくれる」と当時を振り返り答えた。また、映画の中で日常を切り取ったことについても、「イマジネーションって人間の素晴らしい力だと思うんだけど、そのイマジネーションを飛ばせない現実がある。シリア、シリア人っていう言葉で止まっちゃって、その先に行かない。男と女があり、家族ができ、家族が集まり街になり、区になり、県になり、国になる。その国が集まってできたのが世界。突きつめると人間社会、人がベースなはずなのに」と長谷井が話すと、世界中で撮影・取材を続ける安田も「言葉で集団をのっぺらぼうにしてしまう。自分が取材を続けている難民も、もともと難民っていう人はいなかったはずなのに」と話し、「それでもこの作品を見てくれた人は、これからフィリピンのニュースを見た時に、ブランカだ、ピーターだって人の顔が浮かぶ。それって心と心の距離感が全く違うと思います」と話し、長谷井も「そう思ってもらえると嬉しいです」と答えた。
また、安田から「フィリピンに何度も足を運んでいるのはなぜ?」と聞かれると、長谷井は「ひとつは映画を作るため。好奇心とか、見てみたいっていう欲求の中でフィリピンの子供達に出会った。そこで映画を作ろうぜ、っていう話になって、彼らは忘れているかもしれないけれど、自分は約束を果たさなければ、という気持ちがありました。この作品は縁の中で出来上がった。今回は企画から仕上げまで10ヶ月のプロジェクトで短い時間の中での制作だったが、現地の人たちと一緒に作り上げている、という思いがあった。プロデューサーに通訳を雇って欲しいって言ったけど、コーキには通訳はいらない。君のパッションが半減してしまうから、と言われた。ダイレクトなコミュニケーションを大事にした。映画は言語を超えるものだと思っている。“感じる”芸術なので、言葉はそんな重要ではない」とその理由を答えた。安田も自身の旅を振り返り、「カンボジアに初めて行った時に、カンボジアの言葉はもちろん分からなかったけど、その時に感じたのは本当に何かを伝えたい時にはそこを飛び越えたコミュニケーションが通用する、ということでした」と長谷井の経験に自身の経験を重ねた。そこで長谷井も「文化や見た目は決して同じではないけど、お腹が減ったら辛くなるし、大笑いしたり、馬鹿げたことを言ったりするのは一緒。みんな人間だから、どこへ行っても物語は一緒。ボーダーを超えて感じることができるのは、映画の特に良いところ」と芸術論を展開した。
またマニラに行ったことのある安田から、マニラの様子を聞かれると、「劇中でブランカとピーターが歌っているバーがあるんですが、実際ホビットハウスとして経営するバーで撮ったんですね。フィリピンはそういった人たちや色んなジェンダーの人とかが雑多に生活し交わっている、というところに愛があっていいなと思う。クルーにも色々なジェンダーの人がいて、それぞれお互いがエネルギーを発しあっている」とフィリピンの多様性についても言及。そこで、難民について取材をしている安田も「難民の受け入れについて考えるとき、違いに触れるってとても豊かなことで、楽しいことである、ということに気づかされます」と話すと、長谷井から「そのご自身の強さ、モチベーションは何ですか?」と安田に質問が。安田は「一度国に行くと、その子供たちが覚えていてくれる。写真撮影だったり、インタビューは頂き物であると考えています。それに対して何が返せるだろう? もし、もう一度行くことが誰かの喜びになるなら、それが頂き物のお返しになるのかな、と思います」と自身の行動の源を話した。
チームで撮影を行なっていくことを聞かれた長谷井は、「何日か現場をこなしていると、現場に何もしていない人がいる。よくよく見ていると何もしていない。映画はお金がないと作れないという思いから、なんで彼を雇ってんだろうと思ってクルーに聞いてみると、『彼には仕事ないんだもん』と答えた。他の仕事がないから、うちの現場に来ている、ってことだったのだけれど、なんで僕はこれが受け入れられなかったんだろうって思った。また、記録のスタッフが2日目は来なくて。彼女には辛くて乗り切れないっていう理由だったんですが、結構フィリピンでは人がやめちゃう(笑)。ある意味のゆるさ、ゆるい感覚が羨ましいな、って思うこともある。それでもモノは作れるし、動く。独特なリズム感は一つの魅力。時間の流れは違うとは思う」とフィリピン独特の文化を振り返った。
続いて観客からの質疑応答に移り、「様々な国の中で、この国は一番印象に残っている、その理由を教えてください」と聞かれると、長谷井は「それぞれその土地に行けば、いいところが見えるので、どこが一番というのは難しい」と答え、安田は「内戦が始まる前のシリアに行ったんですが、本当に美しいな、風景だけではなく、人なんですよね。ガイドブックを持っていると、勝手に人が寄ってきて案内してくれる。それでバスに乗せられて、勝手にバス代を払ってもらえている(笑)。今、内戦があって、バラバラになっているが、もともと戦地ではなかった場所なのに」と自身の旅を振り返った。「違うところに飛び込んで行くことの大切さに関してはどう思いますか?」という質問には、安田が「初めてカンボジアに行ったのが、高校二年生でした。人身売買の被害にあった同い年の子を取材した。初めての海外で、こんな自分を受け入れてくれるのかと思っていた。でも彼らの方から会話を始めてくれて、彼らの方から共通点を見つけてくれた。私たちは違うところに目が行きがちなんだな、と教えてもらいました」と話すと、圧倒されながらも長谷井は「僕は勇気がないので毎回大変です。行った時点で勇気を持っているけど、持つ前までは毎回躊躇してしまう」と正直に語った。
安田が心に残ったという、ピーターが「みんな目が見えなかったら戦争しないのに」、と話すシーンについて聞かれると「映画にはいろいろな作品があってもいいと思う。でも人と何かをシェアするという意味で、自分が作るものは何か暖かいものがいいなと思う。ピーターと時間を共にして行く中で、ピーターは感じるということを大切にしている、と思った。人が感じ合っていれば、戦争なんかなくなるんじゃないか、言葉というものの先にある“人”というものを想像できなくて情報を飲み込むのではなくて、自分の中で解釈していく。ピーターはとても感じている人で、僕はそのセリフをピーターに言って欲しいと思った」と話した。安田も情報過多気味な現代について「今すごく情報があふれ出ていて、自分が立ち止まって思考してみる、感じてみる、というのが欠落しているな、と思います」と話し、長谷井も「そのことに気づかされてくれたピーターと出会えて本当によかった」と語り、イベントは幕を閉じた。
<安田菜津紀・やすだなつき プロフィール>
1987年神奈川県生まれ。studio AFTERMODE所属フォトジャーナリスト。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、カンボジアを中心に、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で貧困や災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。2012年、「HIVと共に生まれる -ウガンダのエイズ孤児たち-」で第8回名取洋之助写真賞受賞。写真絵本に『それでも、海へ 陸前高田に生きる』(ポプラ社)、著書に『君とまた、あの場所へ シリア難民の明日』(新潮社)。『写真で伝える仕事 -世界の子どもたちと向き合って-』(日本写真企画)。現在、J-WAVE『JAM THE WORLD』水曜日ナビゲーター、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。東京成徳大学非常勤講師。
『ブランカとギター弾き』
7月29日(土)よりシネスイッチ銀座他にて全国順次公開
監督・脚本:長谷井宏紀
出演:サイデル・ガブテロ ピーター・ミラリ ジョマル・ビスヨ レイモンド・カマチョ
配給:トランスフォーマー
ⓒ2015-ALL Rights Reserved Dorje Film