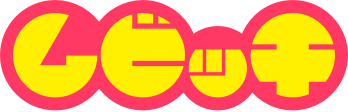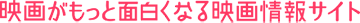混じりけなしの「問題作」だ。土屋太鳳が「オファーを3度断った」という映画『哀愁しんでれら』(2月5日公開)は、観る者を狂わせる強烈な毒に満ちている。

本作は、『嘘を愛する女』等を輩出した、TSUTAYAのクリエイター発掘プログラム「TSUTAYA CREATORS’ PROGRAM FILM」の2016年度のグランプリ受賞作。応募総数422作品のトップに選ばれた脚本の映画化作品となる。
ちなみに、同じ年の受賞作は、準グランプリが『ゴーストマスター』と、ムロツヨシ主演で制作が発表された『マイ・ダディ』(受賞時は『ファインディング・ダディ』)、審査員特別賞は『ブルーアワーにぶっ飛ばす』(受賞時は『ブルーアワー』)だった。このラインナップを見ても攻めた作品が多い印象だが、『哀愁しんでれら』の危険度は群を抜いている。
児童相談所で働く小春(土屋太鳳)。彼女は、幼い時に母が育児放棄して出ていったトラウマから、責任感のない世の母親たちに対して憎悪を抱いていた。そんなある日、祖父が倒れ、家が火事になり、10年付き合っていた恋人の浮気が発覚。一夜にしてどん底に転落した小春だったが、踏切で泥酔した医師・大悟(田中圭)を助けたことから運命が激変。大悟と恋に落ち、彼の娘・ヒカリ(COCO)にも気に入られ、小春は結婚を決意する。どん底から絶頂へ――。シンデレラのような幸せな日々が幕を開けるかと思われたが、徐々に暗雲が立ち込め……。

本レビューではネタバレを挟まずに紹介するが、『哀愁しんでれら』の真価は、いま説明した部分以降、小春を待ち受ける“事件”の数々にある。さらに言えば、母親に捨てられた彼女が、どんな“母親像”にたどり着くのか――。その果てにあるだろう。この部分は作品を観てのお楽しみということで、今回はそこに至るまでの部分を中心に、本作だけが持つ凶暴な魅力を「物語」「演技」「演出」3つに分けて、紹介したい。

「家族」の意味合いが逆転する、醜悪で秀逸な展開
本作を手掛けた渡部亮平監督は、実写映画『3月のライオン』(2017)、映画『ビブリア古書堂の事件手帖』 (2018) 、『麻雀放浪記2020』(2019)等の脚本を手掛けた人物。2012年のオリジナル映画『かしこい狗は、吠えずに笑う』では、監督も務めた。
『哀愁しんでれら』は、元々童話の「シンデレラ」がモチーフとして渡部監督の中にあり、モンスターペアレンツが小学校の校長に包丁を突きつけ「運動会をやり直せ」と迫った事件のニュースを見たことで、構想が出来上がったそうだ。この2つの要素を組み合わせようと思いつく時点で並々ならぬ才能を感じるが、要は最初からスキャンダラスな物語になる運命を背負っていたということ。本作のキャッチコピーにも「なぜその女性は、社会を震撼させる凶悪事件を起こしたのか」とあり、明らかに“危険度”が高い。
作品自体も、冒頭から「ドレスを着た小春が教室の机の上を歩く」という意表を突いたものになっており、事件性を高らかに宣言する。その後、そこに至るまでの物語として、度重なる不幸→大悟と出会い絶頂に至るさまが描かれていく構造だ。しかし、冒頭のシーンが作品全体の「錘(おもり)」となっており、幸せなシーンでもどこかに不穏さを感じさせる。
そして、作品の“本性”が垣間見えるのが、結婚後。小春は、大悟やヒカリの“裏の面”を目にし、自らの倫理観や価値観が揺さぶられ、さらには「良い母親」という理想がのしかかり、次第に壊れていく。
非の打ち所がない優しい人物だと思っていた大悟は、アカデミックハラスメントの気があり、天真爛漫に見えていたヒカリは、エレクトラ・コンプレックス(父親を溺愛し、母親を憎悪する)の要素を持っており、さらに2人の暗部が見えてくることで「家族」がやおら不気味なものに見えてくる、という構成が実に醜悪で秀逸だ。従うか、抗うか――。家族のパワーバランスが常にもぞもぞと胎動し、変容していくさまが恐ろしい。
上に挙げたように、『哀愁しんでれら』は小春・大悟・ヒカリのパワーゲーム的な側面があり、小春はヒカリとの対決を余儀なくされる。さらに、大悟から「母親はこうあるべき」と一種の“調教”を受けるシーンも用意されており、それらを経て小春がどう変化していくか、ひいてはこの家族がどんな帰結を迎えるのか、が大きな見どころだ。

となれば、最重要ともいえるのは、各キャラクターを演じるキャストたち。ここで、渡部監督の4度にわたる土屋へのオファーにつながる。彼女が断った理由は作品を最後まで観ればわかるのだが、同時に観た者からすれば、「土屋太鳳でなければならなかった」と感じてしまうのも事実。それほどまでに本作の彼女は、圧倒的だ。幼少期のトラウマで心の内に怒りと「幸せになりたい」という妄執を抱えており、その結果モンスターと化していく……。
映画デビュー作である『トウキョウソナタ』(2008)、ドラマ&映画『鈴木先生』(2011~13)、吉沢亮らと共演した『赤々煉恋』(2013)など、ある種の狂気をはらんだ役柄を、キャリアの初期で演じてきた土屋。『累 -かさね-』(2018)ではその鬼気迫る演技が話題を集めたが、ルーツはダークなゾーンにあると考えると、さもありなん。『哀愁しんでれら』では、数々の役柄を経験し、より一層厚みが増した狂いっぷりで、観客の目をくぎ付けにする。

『ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜』(2021年5月公開予定)や、バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」などで土屋と共演した田中は、百戦錬磨の実力派だが、本作における「痛み」と「歪み」がぐちゃぐちゃにのたうつ内面の演技は、鳥肌もの。基本的には冷静で穏やかな「完璧な旦那様」なのだが、裏では「バカの相手は疲れるんだよ」と吐き捨て、他者に完璧さを強要する危険人物でもある。小春に対して「食べることしか脳にねぇのかよ!」と絶叫する姿は、俳優・田中圭へのイメージが大きく変わる怪演と言えるかもしれない。

そして、鮮烈な映画デビューを果たしたCOCO。彼女はなんとキッズインスタグラマーで、渡部監督の強い希望によってキャスティングされた。彼女に関してはぜひ新鮮な目で本作での暴れっぷりを観ていただきたく、詳細は控えるものの、とんでもない新星が現れたと畏怖させられるレベルである、ということは伝えておきたい。

画面の隅々まで生き届いた、色彩感覚
練られた物語と、爆発力のある演技。「冷静」と「情熱」が共存する本作のクオリティを底上げしているのが、ルックの部分。つまり映像だ。『哀愁しんでれら』は、映像的な演出に“意図”が細やかに織り込んであり、物語・演技・テーマという「3層」を強く感じさせる。
ひとつ例を挙げるならば、色彩だ。本作は画面内に、常に「赤・青・黄」のどれかが配置されている。黄色は小春の母親が出ていくときに着ていたカーディガンの色であり、大人になった彼女が黄色を身に着けるところに、独特のおぞましさがにじむ。大悟の家のランプは赤色が多く、寝具は紫色。また、小春と大悟のラブシーンでは、その前に「点滴を打つ」というシーンがある。点滴=血を想起させる行為。血といえば「動脈」「静脈」は赤と青で区別されることが多く、この2つの色が交じり合えば、紫になる。それを寝具で表す老獪さたるや。いま述べたものはあくまで私見だが、『哀愁しんでれら』には随所に、深読みしたくなる要素がちりばめられている(“耳”が示すものも、実に意味深だ)。
望まぬ結婚生活を送る主婦が衣食症を患う『Swallow/スワロウ』(2019)でも、原色を大胆に使った演出が目を引いたが、色の使い方・意識は『哀愁しんでれら』にも通じる要素があるように思う。本作のビビッドな色彩は、何もメインのキャラクターや場所に限った話ではなく、時にはエキストラの衣装にも反映されている。このように、画面の隅々まで意識が届いているため、観る側としても居住まいを正されるというか、能動的に画面を注視するようになるだろう。
物語と演技、映像。それぞれの要素が「立っている」作品であり、かつ内容的に攻めまくっている『哀愁しんでれら』。これから作品を観る方は、それぞれのレイヤーが畳みかける“波状攻撃”に備えていただきたい。
文/SYO

『哀愁しんでれら』
2月5日(金) 全国公開
監督:渡部亮平
出演:土屋太鳳 田中圭 COCO 山田杏奈 ティーチャ 安藤輪子 金澤美穂 中村靖日 正名僕蔵 銀粉蝶 石橋凌
配給:クロックワークス
【ストーリー】 児童相談所で働く小春(土屋太鳳)は、自転車屋を営む実家で父と妹と祖父と4人暮らし。幸せでも不幸せでもない平凡な毎日を送っていた。しかしある夜、怒涛の不幸に襲われる。祖父が倒れ、車で病院に向かうも事故に遭い、父が飲酒運転で連行され、火の不始末が原因で自宅は火事になり、家業は廃業に追い込まれ、彼氏の浮気を目撃(しかも相手は自分の同僚)…一晩ですべてを失う。そんな時に出会ったのが、8歳の娘・ヒカリ(COCO)を男手ひとつで育てる開業医の大悟(田中圭)。優しく、裕福な大悟は、まさに王子様のよう。彼のプロポーズを小春は受け入れ、不幸のどん底から一気に幸せの頂点へ。しかしその先には、想像もつかない日々が待っていた…。
©️2021 『哀愁しんでれら』製作委員会