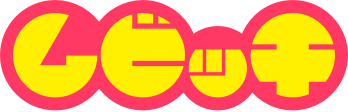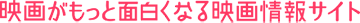イスラム国(IS)との戦闘により瓦礫と化したシリア北部の街コバニでラジオ局を開設し、番組「おはよう コバニ」でDJを務めた20歳の大学生ディロバンを追ったドキュメンタリー『ラジオ・コバニ』が5月12日より公開される。このほど、熊本や福島など日本全国のラジオDJや著名人から応援コメントが寄せられた。

ISとの戦闘で廃墟と化したシリア北部の街・コバニで手作りのラジオ局をはじめる大学生のディロバン。ラジオから聞こえる彼女の「おはよう」が、今日も街に復興の息吹を届ける。トルコとの国境に近いシリア北部のクルド人街コバニは、2014年9月から過激派組織イスラム国(IS)の占領下となるも、クルド人民防衛隊(YPG)による激しい迎撃と連合軍の空爆支援により、2015年1月に解放された。人々はコバニに戻って来たが、数カ月にわたる戦闘で街の大半が廃墟と化してしまった。そんな中、20歳の大学生ディロバンは、友人とラジオ局を立ち上げ、ラジオ番組「おはよう コバニ」の放送をはじめる。生き残った人々や、戦士、詩人などの声を届ける彼女の番組は、街を再建して未来を築こうとする人々に希望と連帯感をもたらす。監督は、自身もクルド人のラベー・ドスキー。地雷や戦車を越えコバニに赴き戦地での撮影を敢行、クルド人兵士によるIS兵士の尋問にも立ち会った。本作を、戦死したクルド人兵士の姉に捧げている。
このたび、ラジオの第一線で活躍するレイチェル・チャンやロバート・ハリスをはじめ、コミュニティFMでラジオ DJを務める大学生や、最後まで臨時災害FMに携わったラジオスタッフなど、全国のラジオDJより熱い共感と
応援コメントが寄せられた。
■レイチェル・チャン(ラジオパーソナリティ)
思わず目を背けたくなる悲惨なシーン。でもそんな悲惨な日常に幼い子どもからお年寄りまでもがさらされている現実。映し出される声なき声と生き残った者たちの声のコントラスト。若きラジオDJの発信する姿を世界中の多くの人に見てもらいたい…。
■ロバート・ハリス(ラジオDJ/作家)
戦争で荒廃したシリアのコバニの街にこだまする「おはようコバニ」の声。傷ついた人々に元気と癒しを与えるトークと音楽。同じラジオの世界で働くぼくにとって、このドキュメンタリーはラジオの役割、ラジオの本質、ラジオの心を改めて考えさせられる作品でした。愛情溢れるタッチで描かれた、珠玉の物語です。
■武村貴世子(ラジオDJ/国連UNHCR協会広報委員)
この声が、この言葉が、この音楽が、あなたに届きますように。彼女の想いに、同じラジオDJとして共感が止まらなかった。傷ついた街に響く彼女の生きている声。それこそが希望だ。
■宗田勝也(京都三条ラジオカフェ『難民ナウ!』代表)
難民問題が天気予報のようになってしまった世界。傷ついた人への祈りが、傘を持って出るかを決める程度に軽くなっていないだろうか?この映画は、人の生と死のことを、いま一度私たちの耳元に近づけようとしてくる。
■ゆあさかな(千葉県・市川うららFMラジオパーソナリティ)
戦闘で瓦礫と化した街で彼女のラジオ、そして彼女の声は街の人々にとって「希望」であった。それは日本の震災復興とどこか通ずるものを感じた。ラジオ文化が下火になっている日本において、主人公の彼女と同じ世代の若者がラジオの魅力を再発見できる貴重な映画である。
■牧野篤史(兵庫県・FM尼崎ラジオDJ)
「音」は力になる。「音」は、街やそこに住む人たちに、強さや、ぬくもり、癒しを与えたり、想像する力と創造する力をくれる。この映画は、ラジオが、戦争で疲弊したコバニの街を支える、その力を感じさせてくれる。
■村上隆二(熊本県・ラジオDJ/ディレクター)
「戦争に勝者などはいない。どちらも敗者だ」という言葉は、戦争を知らない僕に重く響いた。目を覆いたくなる映像。でも、それは現実。戦争がいかに残酷で悲惨で愚かなのか痛感した。厳しい環境の中で常に住民に寄り添い、勇気と希望、そして励ましの言葉を送り続けた。その様子は日本でも災害の際に開局した臨時災害放送局とオーバーラップし、忘れてはならないことを思い起こす映画だ。
■桑原翔(神奈川県・湘南マジックウェイブラジオDJ/文教大学4年生)
崩壊した建物。悲惨な姿の遺体。腐臭に鼻を塞ぐ子供達。目を背けたくなる現実がコバニにあった。この中で、ディロバンさんのラジオ番組は人と人をつなぐ希望となっていた。命を伝える力強さは国境・人種を超えて胸に響いた。音楽と言葉、そして「伝えたい」という想いの力強さを感じた。
■日比野純一(兵庫県・FMわぃわぃ理事)
コミュニティラジオが伝えるのは、自分たちが暮らす社会の今。戦火で廃墟と化したクルドの街の片隅で始まった小さなラジオ局もその一つだ。瓦礫の中から人々は立ち上がり、日常の暮らしを取り戻していく。『ラジオ・コバニ』はそうした営みに光を照らす希望の声である。
■今野聡(福島県・臨時災害放送局南相馬ひばりエフエム元スタッフ)
戦火の中にも、災害後の町にも、人々の小さな暮らしがある。叫び、泣き声、笑い、男と女、音楽…。消えそうになるコバニの町を未来へつなげたいという女子大生の想いは、人々の声をつむいでいく。ラジオが届ける小さな声だからこそ伝わる、リアルな戦争。東北で開局し閉局していった災害FM各局が成し遂げようとしたことも、同じだと思います。
以下は各界著名人の絶賛コメント。
■久米宏
シリア内戦は現在進行形だ。その最中に、よくぞ撮影してくれたと、感謝する。タイトルは可愛いが、物凄い映画だ。ラジオを聴くのは息をするようなものだと、改めて思う。クルドの人々の呼吸を感じることが出来る。
■今日マチ子(漫画家)
人は死に、物体となって放り出され、街は深く傷つけられる。そんな世界に流れるラジオ。戦争を語るとき、感動はいらない。ただ、生きることを手放さない。必要なのは希望だと、ささやかに、力強く教えてくれた。
■荻上チキ(評論家・ラジオパーソナリティー)
美しい故郷・コバニが、戦争のある日常へと変えられた。家族が殺され、友人の首が晒され、遺体の異臭が広がり、爆発音が鳴り響く。コバニを愛する女性が、ラジオの流れる日常をつくった。家を建て直し、兵士が職人へと戻り、パンの匂いが漂い、軽快な音楽が流れる。人々をつなげたラジオの、人々と共に進んでいく街の、確かな歩み、大切な記録。
■ラブリ(モデル・アーティスト)
灰色の空は色んな顔をした
悲しい心でできていた
空は知らなかった
鮮やかな色をした言葉と
柔らかな光のような声が
全て包み込んでいたことを
空は両手いっぱいに
強く抱き締められていたのだ
それは、本当にいつも。
■安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
色彩が奪われた街の中、誰しもが傷を抱えて生きていた。だから、声をあげずにはいられない。そんな彼女の言葉が光となり、取り戻されていく街の息吹をそっと、包み込む。どんな地にも再び、緑が芽吹き、日常という花が咲く。その明日に、希望を託したくなる。
■桜木武史(ジャーナリスト)
破壊され尽くした町を歩いていた私に一人のクルド人が口にした言葉が印象的だった。「町が破壊されたが、土地があれば復興はできる」 復興への道のりの険しさ、それを乗り越えようと奮闘する人々の姿に私は胸を打たれた。この作品を鑑賞することで私が実際に目にしたコバニの力強さを感じてほしい。
■長野智子(キャスター)
多くの人が「正視に耐えられない」と思うだろう。『ラジオ・コバニ』には、バラバラになった、あるいは黒焦げになった遺体が無数に映し出される。報道の仕事を通じて、パレスチナや災害現場などで、ご遺体に接することはあっても撮影したことはない。万が一映り込んでも、視聴者が目にしないよう画像処理を加えて放送する。しかし、ドスキー監督は言う。「ああいう死体を5分と見ていられないなら、死体に囲まれて何カ月も生きなければならない子供の気持ちは感じとれない」と。『ラジオ・コバニ』は報道などでは伝わらない「生の戦争」そのものである。コバニの惨状に打ちのめされ、IS兵士の身勝手な言い分に衝撃を受けた私たちは、絶望以外の言葉が思い浮かばないコバニの街に響く、女子大生ディロバンの声にすがるように希望を探す。そしてそんな戦地であっても、人間がいる限り、笑顔や歌が存在することに救われるのである。
■ピーター・バラカン(ブロードキャスター)
これがドキュメンタリーと思いたくないほど悲惨な状況のコバニはシリアとトルコの国境の町。外を歩くこともままならない地元の人たちの姿に 3.11後の東北を重ねて見てしまいました。彼らにささやかな力を与える日常の放送は理想的な形のラジオかも知れないな…
■木内みどり(女優)
「木内みどりの小さなラジオ」。テレビがなかった頃、一台のラジオを家族みんなで聴いていた、夏は暑く冬は寒く夜は暗かった時代の静かな時間。スタジオもスタッフも抱えない、ひとりで作るラジオ番組。シリアの町コバニに住む20歳の大学生ディロバンがやれたように、わたしにも、あなたにも作れるラジオ番組。大手メディアから脱出しましょう。
『ラジオ・コバニ』
5月12日(土)より、アップリンク渋谷、ポレポレ東中野ほか全国順次公開
監督・脚本:ラベー・ドスキー
配給:アップリンク