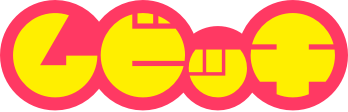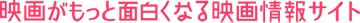2017年の第74回ベネチア国際映画祭にて銀獅子賞(最優秀監督賞)を受賞した、新星グザヴィエ・ルグラン監督のデビュー作『ジュリアン』が、1月25日より公開される。このほど、2児の母で女優の長谷川京子や、人気劇作家の長塚圭史、日本を代表する女性監督の西川美和監督と呉美保監督、『弧狼の血』を手掛けた白石和彌監督らより本作を絶賛するコメントが寄せられた。

本国フランスで40万人動員のロングランヒットとなった本作は、家族の関係を繊細に描いたサスペンス。主人公は、離婚した父親アントワーヌと母親ミリアムの間で揺れ動く、11歳の息子ジュリアン。親権は共同となり、ジュリアンは母を守るために必死で父に嘘をつき続けるが、物語は想像を超える衝撃の展開をみせていく。
監督は、本作で長編監督デビューとなる、フランス映画界の新星グザヴィエ・ルグラン。離婚した両親の間で葛藤する主人公ジュリアンを、本作が映画初出演となったトーマス・ジオリアが演じる。
著名人 絶賛コメント
■呉美保(映画監督)
終始、恐怖と困惑。鑑賞後、号泣と放心。子を持つ母の立場では、受け入れ難い物語。なのに、またすぐ観たくなった。子、母、父、それぞれの痛みを、いまいちど感じ直したかった。2度目の鑑賞後、救済すべきは父なのだと、強く思った。
■治部れんげ(ジャーナリスト)
暴力が沁み込んだ日常生活から逃れようとする親子の姿には、日仏の法制度・社会規範の違いを超えた普遍性があります。「ジュリアンは私だ」と思う人も少なくないでしょう。
■白石和彌(映画監督)
冒頭から支配する緊張感と、とんでもない瞬間を目撃してしまうラスト。映画を見て呆然とするよりないが、これは遠い国の話ではなく、日夜私たちのすぐ隣でも起こっている。ジュアリアンの優しさと強い目線が頭から離れない。
■長塚圭史(劇作家・演出家・俳優)
淡々とした描写にいつの間にか引き込まれ、痛むような恐怖を味わうことになってしまった。この恐怖の正体は、表層だけでは何もわからないということにある。本当の原因がどこにあるのかが巧妙に見えにくい為、つまり家族の責任の追求がいかに困難であるかというリアリズムの上に立脚しているがゆえに、私もあなたも、生々しい痛みを伴う恐怖を味わわされるのではないか。これが長編初というからまさに気鋭の新人である。
■西川美和(映画監督)
両親の不和の狭間でじっと堪えるジュリアンのまなざしの暗さに、言葉を失った。「わたしも……」とかつての悲しみがぶり返す人も多いだろう。「うちの子も……」と我が子の顔を覗き込む人も多いだろう。そしてジュリアンの未来を明るくするために、子供たちをもう一度ちゃんと抱きしめたくなるのではないか。
■西牟田靖(ライター、作家)
フランスでは離婚後も原則、面会交流や共同親権が認められる。この映画はその制度の重みを逆説的な意味で考えさせられる。
■長谷川京子(女優)
子供を守ることが親の務めである、と、そんなことは誰もが分かっている。それでも親だからと言って完璧な人間にはなれない。父親に怒鳴り問い詰められ、それでも母親を守ろうと口をへの字にして耐える。姉と母と新居を探す場面では、新しい生活に心を踊らせ頬を緩める。11才と言う年頃の男の子はもちろん子供であり、そして誰よりも状況を敏感に読み取っていた。それを言葉少なく、ジュリアンは表現してくれました。無知が故に、無垢が故に、防御の仕方を知らず剥き出しになったジュリアンの心に傷がついていく様を見ることがとても辛かった。
■深澤真紀(獨協大学特任教授・コラムニスト)
かつて「クレイマー・クレイマー」では、離婚による母親の自立と、育児する父親の奮闘が描かれた。40年後の「ジュリアン」では、離婚によって守られるべきなのは誰なのかを問いかけている。
『ジュリアン』
1月25日(金)より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次公開
監督・脚本:グザヴィエ・ルグラン
製作:アレクサンドル・ガヴラス
撮影:ナタリー・デュラン
出演:レア・ドリュッケール ドゥニ・メノーシェ トーマス・ジオリア マティルド・オネヴ
配給:アンプラグド
【ストーリー】 両親が離婚したため、母ミリアム、姉と暮らすことになった11歳の少年ジュリアン。離婚調整の取り決めで親権は共同となり、彼は隔週の週末ごとに別れた父アントワーヌと過ごさねばならなくなった。母ミリアムはかたくなに父アントワーヌに会おうとせず、電話番号さえも教えない。アントワーヌは共同親権を盾にジュリアンを通じて母の連絡先を突き止めようとする。ジュリアンは母を守るために必死で父に嘘をつき続けるが、それゆえに父アントワーヌの不満は徐々に溜まっていく。家族の関係に緊張が走る中、想像を超える衝撃の展開が待っていた。
© 2016 – KG Productions – France 3 Cinéma