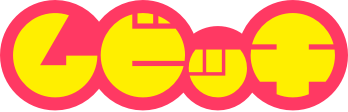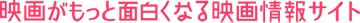テレビアニメ化も発表されたヤマシタトモコ氏による人気漫画を、俊英・森ガキ侑大監督が岡田将生・志尊淳・平手友梨奈を迎えて実写映画化した『さんかく窓の外側は夜』が、1月22日から劇場公開中だ。

本作は、「霊を視認できる男」と「霊を祓える男」のコンビが、「人を呪える女」と対峙していく物語。幼少期から霊が見える体質に悩まされる三角(志尊)は、除霊師の冷川(岡田)にスカウトされ、助手になる。なんでも、三角と“つながる”と冷川は、霊の姿がくっきりと見えるのだという。そんな折、刑事・半澤(滝藤賢一)から持ち掛けられた事件の調査にあたった冷川と三角は、呪いを操る女子高生・非浦英莉可(平手)の存在に近づいていく――。

実写版『さんかく窓の外側は夜』は、2時間の枠に収めるため、原作からいくつかの改変はあるにせよ、ストーリーの大筋は変わっていない。独特の雰囲気をまとった、異端の(多少のホラー要素を含んだ)ミステリーといえるだろう。

「心霊」を扱いつつ、浮かび上がるのは「人の怖さ」
「心霊」や「呪い」は、リアルベースからがっつりファンタジーまで、日本の小説・漫画・映画・舞台など多数のコンテンツで取り上げられてきた題材。『リング』や『呪怨』もそうであるし、今現在も「呪い」と「呪術師」の戦いを描いた漫画「呪術廻戦」がスマッシュヒットを飛ばしているなど、いつの時代も人々の興味関心の対象となってきた。黒澤明監督の『羅生門』の原作である芥川龍之介の「藪の中」にも、巫女に乗り移った死霊の描写がある。
ただ、『さんかく窓の外側は夜』というコンテンツ(漫画/実写映画共に)が興味深いのは、極めて近代的な雰囲気の中に、「心霊」「呪い」という要素を混ぜ込んでいること。従来の国内作品ではこれらの題材を描く際、土着のものと結びつけた物語や世界観になることが多かったが、本作からはそんな風合いが感じられない。土臭さや古びた雰囲気とは無縁の、からりと乾いた無機質な雰囲気は、観賞者に新鮮な驚きをもたらすのではないか。
たとえば、先日実写ドラマ化された「岸辺露伴は動かない」は、「森の神」や「禁止された言葉」という超常的な恐怖を描くため、作品自体が日本の歴史、土地勘といったものを帯び始める。それに対し、『さんかく窓の外側は夜』で描かれる“怖さ”は、あくまで「人」だ。霊も呪いも、元をただせば人から出ずるもの。その結果、「いまの時代の人間の暗部」にダイレクトにつながっていく。漫画から映画に変換されていくときに、「SNSにたまる呪詛」といった描写がより強化された点から見ても、この作品が向かう方向は明白だ。
そしてその先に、「カルト教団」という謎めいた存在が浮かび上がったとき、『さんかく窓の外側は夜』の実像が顕現する。本作が描く「諸悪の根源」は、あくまで人だということ。そういった意味では、純粋なホラー作品というよりも、『セブン』などのサイコサスペンスの文脈で見ていった方が、しっくりくるだろう(原作ではそこに『イット・フォローズ』的な怖さも盛り込まれている)。
キャラクター描写も、作品のテーマ性とリンクしている。冷川がある出来事から人間らしい感情が「わからない」ということ、非浦が父親の指示で“呪い屋”になったことなどが掘り下げられていく中で、心霊を取り上げつつも「人に毒された被害者たちの物語」であることが見えてくるのだ。
原作ではそこに、ほのかにBL要素を織り込み、冷川が三角に触れる/中に入る(霊的な手で、魂に干渉するような意味合い)ことで、霊への感度を高めるというオリジナリティあふれる設定を付加。とはいえ飛び道具的なアイデアでは決してなく、「人と人が絆で結ばれる大切さ」を感じさせるフックになっているところが、非常に上手い。余談だが、原作と実写映画では三角のキャラクター設定が微妙に異なっているので、比べてみるのも一興だ。

感度の高いメンバーによって生み出された、「次世代の映画」
ここまでは原作漫画と実写映画に共通する要素を中心に述べてきたが、映画版独自の魅力とは何だろうか? それは、ビジュアル面をより先鋭的に進化させていることではないか。映画『さんかく窓の外側は夜』を観ると、冒頭からスタイリッシュな映像表現の“連射”に、一気に呑み込まれるだろう。
暗闇の中に蛍光色の三角形が浮かび上がる作品全体のキーとなるシーン、意味深なビジュアルを小刻みに並べていく洋風な映像演出、三角形がループする螺旋階段、犯罪現場の雨の切り取り方、血が飛ぶシーンの無音&スロー演出等々……。ハイセンスな仕掛けの数々が、「いまの映画」を超えた「次世代の映画」感を、強烈に喚起させる。
森ガキ監督は、ゲーム「グランブルーファンタジー」や日清カップヌードルのCM等で、才気を発揮してきた人物。長編デビュー作『おじいちゃん、死んじゃったって。』でも、ローカルな家族劇の中に、観客の目を引く印象的なカットを織り交ぜていた。『さんかく窓の外側は夜』という物語と彼がかけ合わさったとき、映像的な“目”がより研ぎ澄まされた印象だ。
岡田将生、志尊淳、平手友梨奈など、“いま”を背負った面々とのコラボレーションも、興味深い。普段着とはやや異なる、黒を基調としたデザイン性が高い衣装を、岡田・志尊・平手の面々が着こなすことで、リアルとファンタジーの中間のような、不思議な浮遊感が醸し出されているし、冷川の事務所は照明からマグカップに至るまで、インテリア好きの心をくすぐるモダンなものが並ぶ。

画面に映るすべてを、「カッコいい」要素でまとめているため、本稿の前半で述べたような「土臭さ」から離れた原作漫画の魅力が、より際立っているのだ。いわば、ビジュアル面でのシンクロ――“映像脳”での作品理解度が、実に高い。漫画の実写化においては、どうしても「再現」に重きを置きがちだが、本作は原作のビジュアルを念頭に置いたうえで、さらに先に行こうとする気概を見せつけている。ゆえに、三次元の“肉体”をまとった物語として、しっかりと成立しているのだ。
ちなみに本作の衣装はドラマ「カルテット」や「凪のお暇」のBabymix、ヘアメイクは染髪を専門とする“カラリスト”の澤田梨沙が担当。さらに、主題歌は気鋭ミュージシャン「ずっと真夜中でいいのに。」が手掛けた。同バンドが醸し出す“最先端”のサウンドに、映像が負けていないどころか相乗効果を生み出しているのも、注目すべきポイントだ。
監督・キャスト・スタッフ――トレンドを「作る」側のメンバーが集結した実写映画『さんかく窓の外側は夜』は、見えないものが「見える」人々の物語であり、全編通して「魅せる」作品でもある。作品を観賞する際はぜひ、意匠の数々に目を配っていただきたい。(文/SYO)
『さんかく窓の外側は夜』
1月22日(金) 全国ロードショー
監督:森ガキ侑大
原作:ヤマシタトモコ「さんかく窓の外側は夜」
脚本:相沢友子
主題歌:ずっと真夜中でいいのに。「暗く黒く」
出演:岡田将生 志尊淳 平手友梨奈 滝藤賢一 マキタスポーツ 新納慎也 桜井ユキ 和久井映見 筒井道隆 北川景子
配給:松竹
【ストーリー】 書店で働く三角康介(志尊淳)は、一見普通の⻘年だが、幼い頃から幽霊が視える特異体質に悩まされていた。ある日、書店に除霊師・冷川理人(岡田将生)がやってくる。「僕といれば怖くなくなりますよ」の一言で、三角は冷川と除霊作業の仕事を共にすることに。そんな中、二人は刑事・半澤(滝藤賢一)から、ある連続殺人事件の話を持ち掛けられる。調査を進めるうちに、二人はある言葉にたどりつく…。「ヒウラエリカに…だまされた…」。この事件には、呪いを操る女子高生・非浦英莉可(平手友梨奈)の影が潜んでいたのだ。果たして“ヒウラエリカ”とは何者なのか?事件との関係は?死者からの謎のメッセージを解き明かそうとする冷川・三角の二人は、やがて自身の運命をも左右する、驚愕の真実にたどり着く。
©2021映画「さんかく窓の外側は夜」製作委員会 ©Tomoko Yamashita/libre