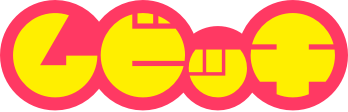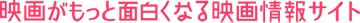第70回カンヌ国際映画祭にて、ある視点部門審査員賞を受賞したミシェル・フランコ監督最新作『母という名の女』が6月16日より公開となる。それに先立ち、6月8日にメキシコ大使館にてトークイベント付き試写会が行われ、「アダルトチルドレン」という言葉を日本に紹介し広めた第一人者で、多くの関連本を出版している精神科医の斎藤学が登壇した。

本作は、母と娘の確執を描く衝撃のミステリー。2回観たという斎藤は、「周りの女性に聞くと、みんなさわやかな後味の映画だったというので観直したんです。すると、この映画は長女が語り部で、長女の目線で見てみるとピタッとくるんです」と話し、「この作品は私の中で“母娘もの”というくくりの中に入る。イングマール・ベルイマン監督の『秋のソナタ』や是枝裕和監督の『誰も知らない』や近藤ようこ著の「アカシアの道」を思い出した」と過去の名作を引き合いに出し解説した。
また、斎藤はポスターを指さし「皆さんはこのようなモンスターマザーは作られたもので、世間にはいないだろうと思うかもしれない。しかし、私は家族療法家という仕事をしているから、この種の母たちが確実にいることを知っています。トキシックペアレンツ(毒親)、トキシックマザーと呼ばれたりしています。そういう人格の人はナルシシズム(自己愛)に攻撃性が加わっている」と指摘。さらに、「伝統的な家族の中での母というのは自己犠牲を強いられることが多く、女性もどんどん活躍していきましょう、という今の世の中と合わなくなっているのです。それで今もこれからも、この映画の中の母のような存在が増えています」と明かし、「人間の深いところの一つが性行為だと思うんですけれど、その部分でも女性が自己主張的になっています。日本の女性も例外ではありません」と述べた。
本作の中で、母が娘から奪った赤ちゃんに対してある衝撃的な行動をとるが、その行動に会場の観客の多くが理解できないと答える一方で、斎藤は「あの辺がこの種の母たちの特徴です。まさかそこまでやらないだろうということをパッとやれちゃう、という人格像があるんですよ」と精神科医の目線で分析。そういった“ボーダーライン”(=不安定な自己、及び他者のイメージ、感情・思考の制御不全などを特徴とする障害のこと)の人を見分けるコツとして、「例えば、あなたにボーダーラインの友人がいるとすれば、その人はまるで2つの人格を持っているみたいに見えます。“あなただけが私の理解者よ”とベタベタ寄ってきて、無二の親友のように思わせておきながら、何かの件でその人に忠告したりすると、態度がガラリと変わる。そしてあなたを敵とみなして深夜電話や脅迫の手紙であなたを非難するようになる。実はそういうボーダーラインの人って、複雑に見えるけど4歳5歳児がそのまま大きくなってしまった、という風に見るとよくわかる。ソシオパスとかサイコパスとかみたいに反社会性があるわけではない。他の人から自分が評価されているということに過敏すぎて、自分のある部分が否定されるとパニックを起こしちゃう。そういう彼らをみるとほっとけなくなっちゃうので、捨てることもできない。悪気はなくて、子供還りしちゃってるから」と解説し、本作で描かれる毒親についての医師ならではの意見に、観客は終始聞き入っていた。最後に、メキシコ大使館からメキシコ産ワインと料理が振舞われ、本作の感想や意見を交換し合い、イベントは幕を閉じた。
『母という名の女』
6月16日(土)より、ユーロスペースほか全国順次ロードショー
監督・脚本・製作:ミシェル・フランコ
撮影:イヴ・カープ
出演:エマ・スアレス アナ・ヴァレリア・ベセリル エンリケ・アリソン ホアナ・ラレキ エルナン・メンドーサ
配給:彩プロ
【ストーリー】 海沿いの家に二人で暮らす姉妹。17歳の妹・バレリアは妊娠しており、姉・クララは離れて暮らしている母親・アブリルを電話で呼び寄せる。お腹の中の子供の父親は、クララが経営する印刷所でアルバイトしていた17歳の少年・マテオ。姉妹の元に訪ねてきたアブリルは、クララやマテオと会話を重ね、バレリアの不安を和らげるように接し、母親に不信感を抱いていたバレリアも徐々に母を信用し、そして無事に女の子が生まれ、カレンと名付けられる。バレリアの代わりにカレンの世話をしているうちに独占欲がアブリルの中に芽生える。カレンを自分の管理下に置こうとするアブリルに反発しはじめるバレリア。娘との関係が悪化していく中、ついにアブリルは深い欲望を忠実に遂行していく。
©Lucía Films S. de R.L de C.V. 2017