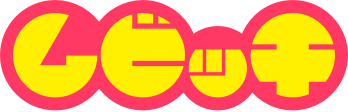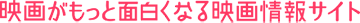日本で生きる二人のクルド人青年を5年以上取材した、日向史有監督のドキュメンタリー映画『東京クルド』が、7月10日より公開される。このほど、予告編がお披露目となり、併せて、各界著名人より本作へのコメントも寄せられた。
本作は、故郷での迫害を逃れ、小学生のころに日本へやってきて以来、難民申請を続けるトルコ国籍のクルド人、オザン(18歳)とラマザン(19歳)を5年以上にわたって追ったドキュメンタリー。日本では2021年5月、入管の収容者に対する非人道的な行為や環境を問題視する世論の高まりを背景に、入管法改正案は事実上、廃案となった。しかし「難民条約」を批准しながら難民認定率が1%にも満たないというのが日本の現状だ。オザンとラマザンも、入管の収容を一旦解除される「仮放免許可書」を持つものの、立場は“非正規滞在者”となり、いつ収容されるか分からない。二人は不安を常に感じながらも夢を抱き、将来を思い描いているが、彼らは住民票もなく、自由に移動することも、働くこともできない。また社会の無理解によって教育の機会からも遠ざけられている。そんななか、東京入管で事件が起きた。長期収容されていたラマザンの叔父メメット(38歳)が極度の体調不良を訴えたが、入管は家族らが呼んだ救急車を2度にわたり拒否。彼が病院に搬送されたのは30時間後のことだった。在留資格を求める声に、ある入管職員が嘲笑混じりに吐き捨てた。“帰ればいいんだよ。他の国行ってよ”。5年以上の取材を経て描かれる二人の若者の青春と日常。そこから浮かび上がるのは、救いを求め懸命に生きようとする人びとに対するこの国の差別的な仕打ち。彼らの希望を奪っているのは誰か?救えるのは誰か?が、作品の中で問われている。
予告編は、「入管の中で死にたくない」という衝撃的な言葉から始まり、日本で育った二人のクルド人青年の青春と日常を映し出す。夢に向かってもがく姿、それを阻む大きな壁、差別的な状況の中でも懸命に生きようとする人々の姿。予告編の最後では、「救えるのは誰か…」と問いかける。
■日向史有(監督) コメント
2021年、入管法「改正」案が閣議決定され、審議の末に成立は見送りとなった。しかし、私には、今も日本が難民を排除する方向に向かっているとしか思えない。この原稿を書いている今、ニュースでは収容中に死亡したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの続報が伝えられている。だが、なぜ彼女が亡くならねばならなかったのかについては、未だ明らかにされていない。今回の「改正」案が見送られたからといって、この映画に出演してくれた人たちの置かれている過酷な状況は、何ひとつ変わらない。今回の映画公開にいたるまでには約5年かかった。少しでも多くの人に、日本で生きるクルド人について知ってもらいたいと思っている。





▼著名人 コメント
■温又柔(小説家)
さっさと他の国に行けって?行けるものなら、とっくにそうするよ。いっそ、たどり着かなければよかった。――これ以上、この国に、絶望させられませんように。今日もきっと、誰かが必死に耐えている。こんな日本で、私たちはいいの?知らないふりは、もうできない。
■せやろがいおじさん(お笑い芸人/YouTuber)
八方塞がりの絶望的な状況においても、僅かな希望に向かって懸命に日々を過ごしている二人のクルド人青年。そんな二人に向けて、入管職員が放った言葉が耳から離れない。「帰ればいいんだよ。他の国行ってよ他の国」この言葉が象徴するのは、入管の「排除の体質」だ。入管が排除の対象にしている「人」がどのような存在なのか。この作品を通じて多くの人に見て、知ってもらいたい。
■髙谷幸(東京大学教員)
「仮放免許可書」——入管によるたった一片の紙切れが、若者の日常生活のあらゆる側面を規定し、彼らの抱く夢、淡い期待をも蝕んでいく。彼らを追い詰めることで、この国は、そして「私たち」は、何を守ろうとしているのか。
■鴇沢哲雄(フリーライター「日本で生きるクルド人」)
差別と無理解、入管行政の厚い壁…。戸惑いと絶望の中でもなお、生きる希望とクルドの誇りを捨てない若い二人。オザンとラマザン。その問いかけは私たちに突きつけられた刃のようだ。
■中島京子(小説家)
18歳と19歳。対称的な二人の、けれど等しく理不尽な現在に心を掻き乱される。摘み取ろうとしても、踏み潰そうとしても、明日に向かって伸びていく生のエネルギーは壊せない。彼らの未来を奪おうとする日本という国の試みは、ただひたすら残酷なだけで、そもそもの始めから失敗しているように見える。彼らに在留資格を。日本で生きていく未来を。もし、それができないのなら、滅びるのは彼らではなく、この日本だ。
■西森路代(ライター)
ラマザンとオザン。二人のクルド人の若者は、前に進んだかと思えばすぐに壁にぶつかる。彼らを立ち止まらせるのはこの国の矛盾だ。映画を見て動くべきは自分たちだと思った。
■ハン・トンヒョン(日本映画大学准教授・社会学)
今ここで自由を求めて格闘する二人の姿から見えてくる、この社会の不正義とこの世界の不条理。その壮絶に重ねる傲慢を恥じつつも共振してしまったのは、在留資格はあっても国のない私にも身に覚えのある理不尽さと青春の痛みがそこにあったから。彼らも、そして大人になった私も、今ここを生きている。今ここに生きるすべての人が見るべき、痛切な青春映画。
■望月衣塑子(「東京新聞」記者)
まだ若いオザンに入管職員は「他国へ行ってよ。帰ってよ」と平然と刃を突きつける。これが彼らの日常であり、入管対応の現実であることに怒りと絶望しかない。現在を生きる全ての日本人が観るべきドキュメンタリーだ。
■森達也(映画監督・作家)
帰ればいいんだよ。他の国行ってよ。入管職員が彼らに浴びせる言葉を聞きながら、僕はこの国に生まれたことが本当に恥ずかしい。苦しい。腹立たしい。観終えて思う。日本国民の半分が、いや10分の1が、いや100分の1でもいい、とにかくこの映画を観てオザンとラマザンの夢と希望を打ち砕く冷酷さを目撃したのなら、きっと気づくはずだ。入管職員は日本国籍を持つ自分たち自身でもあるのだと。
■綿井健陽(ジャーナリスト・映画監督)
名古屋の入管施設で亡くなったスリランカ人女性・ウィシュマさんの顔と名前を憶えている人は多いだろう。ならば、この映画に現れるクルド人のオザンとラマザン、そしてメメットの顔と名前も憶えておいてほしい。彼らが日本でどんな扱いを受けてきたのか、彼らがこれから日本でどう生きていけるか。入管の中も外も、日本社会とつながっている。
『東京クルド』
7月10日(土)より、渋谷シアター・イメージフォーラム、大阪・第七藝術劇場にて公開、以後全国順次公開
監督:日向史有
配給:東風
©2021 DOCUMENTARY JAPAN INC.b