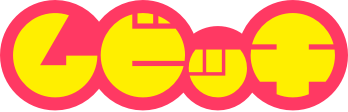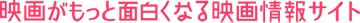第69回カンヌ国際映画祭パルムドール(最高賞)受賞作『わたしは、ダニエル・ブレイク』を手掛けた、イギリスを代表する名匠ケン・ローチ監督の最新作『家族を想うとき』が12月13日より公開される。このほど、各界著名人より本作を絶賛するコメントが寄せられた。

本作は、グローバル経済が加速する中で変わっていく人々の働き方と、時代の波に翻弄される“現代の家族の姿”を描いたヒューマンドラマ。
▼著名人 絶賛コメント
■山本太郎(れいわ新選組代表)
小さな幸せさえも容赦なく破壊する搾取の連続。これは遠く離れた国の話ではない、私たちの話だ。
■小川彩佳(キャスター)
すれ違いながら想い合い、繋ぎ止めようと手を伸ばし、それでもじわり壊されていく。ただ幸せでいたいだけなのに、なんで、なんで、なんで…。ラストシーンの余韻が止まりません。これは日本も「じぶんごと」かもしれない。
■柳澤秀夫(ジャーナリスト)
これは他人事じゃない!効率優先のゆがんだ社会に翻弄されながらも、ささやかな幸せを求めて懸命に生きようとする家族。あまりにも切ないその姿に思わず「がんばれ!」と声援をおくらずにはいられなくなった。
■茂木健一郎(脳科学者)
誰も不幸になりませんように。祈るような気持ちで物語に没入した。厳しい現実のひんやりとしたリアリティの中から、人の心の温かさがしみ出てくる。衝撃のラストシーンに巨匠の怒りと愛を感じた。傑作を超えた神品。
■ピーター・バラカン(ブロードキャスター)
映画が終わる頃にはこの家族が肉親のような気持ちになります。ブラック企業というよりブラック世界。これはケン・ローチならではの愛情に溢れた作品で、道に迷った人類に対する警鐘でもあります。
■荻上チキ(評論家/TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」パーソナリティ)
誰も望んでいないのに、すれ違う家族たち。彼らが薄情なのか?いや、そうではない。そうさせたものの正体に、じわりじわりとカメラが近づいていく。
■柏木ハルコ(漫画家「健康で文化的な最低限度の生活」)
物語には常に現実を描く一面と妄想を描く一面があるが、この映画には妄想の要素はほとんどない。ケン・ローチ監督はここから目をそらすことを許さない。私たちの“働き方”はこれでいいのだろうか?私たち一人一人が向き合うべき重い問いである。
■中川敬(ミュージシャン/ソウル・フラワー・ユニオン)
前作『わたしは、ダニエル・ブレイク』公開後に引退撤回したケン・ローチ監督が、新自由主義経済の底辺にある一家の、酷烈な転落と絆を描く。袋小路の家族物語だが、変化を希求する監督の誠実な怒りが、懸命に生き抜く人々の気高い尊厳を立ちのぼらせる。何度も胸が熱くなった。またもや最高傑作。必見!
■森達也(作家・映画監督・明治大学特任教授)
コメントが難しい。何を書いても作品の質量に届かない。ラストの家族の慟哭がいつまでも心に残る。ケン・ローチと同時代に同じ仕事をしている巡りあわせに感謝する。
■想田和弘(映画作家)
前作の『わたしは、ダニエル・ブレイク』で引退すると言っておられたが、撤回して『家族を想うとき』を作ってくれて、本当によかったと思う。現代に生きる私たちにはこの監督が必要だ。可能な限り、作品を撮り続けて欲しいと切に願う。
■武田砂鉄(ライター)
そうなったのはオマエのせいだろ、と突きつけてくる社会。出口はどこにあるのか。出口を塞いでいるのは誰なのか。
■小熊英二(社会学者)
宅配ドライバーの夫と訪問介護の妻。14時間労働、理不尽な待遇、疲労とストレス、子供の不登校。これでもかとばかりの現実のあと、ラスト場面でSorry We Missed You. 音楽なしのタイトな演出が印象的。見れば忘れられない映画になるだろう。
『家族を想うとき』
12月13日(金)より、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次公開
監督:ケン・ローチ
脚本:ポール・ラヴァティ
出演:クリス・ヒッチェンズ デビー・ハニーウッド リス・ストーン ケイティ・プロクター
配給:ロングライド
【ストーリー】 イギリス、ニューカッスルに住むある家族。父のリッキー(クリス・ヒッチェンズ)はマイホーム購入の夢をかなえるために、フランチャイズの宅配ドライバーとして独立。母のアビー(デビー・ハニーウッド)はパートタイムの介護福祉士として、時間外まで1日中働いている。家族を幸せにするはずの仕事が、家族との時間を奪っていき、高校生のセブ(リス・ストーン)と小学生の娘のライザ(ケイティ・プロクター)は寂しい想いを募らせていく。そんななか、リッキーがある事件に巻き込まれてしまう…。
© Sixteen SWMY Limited, Why Not Productions, Les Films du Fleuve, British Broadcasting Corporation, France 2 Cinéma and The British Film Institute 2019 photo: Joss Barratt, Sixteen Films 2019