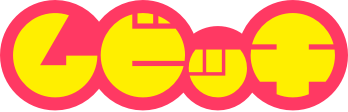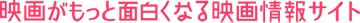近年、国内の映画・ドラマでますます頭角を現している存在。それが、若葉竜也だ。大衆演劇の一家に育ち、幼いころから演技の世界に身を置いていた彼は、自他ともに認めるリアリスト。各方面から引っ張りだこの状況もまるで意に介さず、「自分は何も変わらない」と語る。

浮かれることがないため、手を抜くこともない。だからこそ、若葉の演技は安定感の年季も強度も、ものが違う。盟友である今泉力哉監督と組んだ最新作『街の上で』(4月9日公開)でも、130分ほぼ出ずっぱりにもかかわらず、「下北沢の住人」としてその場に溶け込み続けるという職人芸を披露している。
下北沢の古着屋で働く青年・荒川青(若葉竜也)。淡々と暮らす彼の日常に、「自主映画への出演依頼」という“非日常”が訪れる。映画は青を軸に、彼の周囲を惑星のように廻る4人の女性をおかしみと愛情をこめて描いてゆく。
今回は、若葉に単独インタビュー。今なお成長し続ける彼の“現在”と共に、作品の舞台裏をたっぷりと語ってもらった。
――『あの頃。』、NHK連続テレビ小説「おちょやん」、『街の上で』『くれなずめ』と、2021年は若葉竜也さんイヤーですね。
(笑)。僕自身はそんなに実感がないですね。というのも、たまたま公開が重なっただけだから、意識的ではないし狙ってやったわけでもない。もし計画的に仕込んでいたとしたらもう少し感覚が違ったのかもしれないですが、偶然だからこそ、僕自身は冷静ですね。
――とはいえ、盟友の仲野太賀さんと共に、どんどん勢力を拡大されている気がします。
太賀は僕より戦略的なところはありますが、二人とも昔から戦い方自体は変えていないんですよね。ただ、お互い責任感あることをやらないといけなくなってきた意識はあるし、自分たちで何かを発信できたり、こっちから監督を口説いて面白そうな企画を進めたりできる状況というのは出来上がってきた。昔ふたりでしゃべっていたことが実現しているなという感覚はありますね。
――若葉さんは以前「俳優という自分を俯瞰で見ている」とおっしゃっていましたが、今回の「初主演映画」に対してはいかがですか?
主演だからどうこうということもなかったし、そういった意識も働いていなかったですね。もともと『街の上で』という企画の存在は知っていて、お話をいただいた際に下北沢が舞台で今泉さんだったら面白そう、と思ってお受けして、蓋を開けたら主演だったんです。主演だから飛びついたという感覚もないですし、いつも通り粛々とやりました。
――今泉さんからは、どういった形でオファーがあったのでしょう。
『愛がなんだ』の公開イベントで、今泉さんと僕が映画館でトークショーをする日があったんです。その日の夕方くらいにマネージャーと打ち合わせをしてて、その際に5ページ分くらいの企画書をもらいました。
僕は普段、あまり骨組みや枠組みが見えない映画は台本をいただいてからじゃないとジャッジしないのですが、今泉さんとはものを作る上での温度感が近いと感じていたので、今泉さんとだったら面白いことができそうだなと感じました。そしてトークショーの会場に行ったら、今泉さんが「企画書、読んだ?」と聞いてきたので「読みましたよ。第1稿が上がったらふわっと送ってください」というお話をさせていただきました。
――「今泉監督だから」も大きいかと思うのですが、『街の上で』の物語自体のどういう部分に、惹かれましたか?
何も起きないであろうところですね。『サッドティー』(13)当時から今泉さんの映画を観ていた身としては、監督の純度が高そうな匂いがしたんです。「今泉力哉が本当にやりたいこと」をやる企画だと思えて、そこが一番のとっかかりでした。

――今回は大橋裕之さんとの共同脚本で、より“笑い”の要素が印象的だと感じました。おふたりのコラボレーションについては、いかがですか?
今泉さんの映画は喜劇的で、悲劇の要素や悲しいシーンはあるのですが、それが逆に滑稽に思えて面白く見えてくる。観るときのタイミングによって変わっていくという面では、大橋さんとの相性もすごくいいと思ったし、絶対面白くなると思っていました。
ふたりがそれぞれの作品でやろうとしていることって、違うところに見えてじつは同じところにいるような気はするんですよね。
――本作では若葉さんはほぼ出ずっぱりで、セリフもかなり多いかと思います。
最初、今泉さんは「無口な主人公の話をやりたい」と言っていたんですよ(笑)。ほとんどしゃべらずにただ巻き込まれていく主人公はどうかという話で、「いいじゃないですか」と答えたのですが、第2稿が上がってきた時点で滅茶苦茶しゃべっていました(笑)。
――あと、作品を拝見して非常に心地よかったのが、どこまでが指定されたセリフでどこまでが役者から出てきたのものなのかわからない、という生活感や生々しさです。
僕に関してしかわからないですが、自分のパートはアドリブは一個もないんですよ。すべて台本通りに話しています。
――そうなんですね! 衝撃です。
アドリブかどうか分からないと感じる部分は、今泉さんの日常会話の精度の高さだと思います。セリフが結構な量あったとしても、おしゃべりなやつには見えない。「無口」という設定を残したままこの分量のセリフが欲しい、と今泉さんも話していました。
今泉さん自身にもそういうところがありますね。すごくたくさん話す人だけど、おしゃべりのイメージがない。そうした今泉さんの“色”が主人公の青に反映されているんじゃないかな、と思いました。
――確かに。そういう意味では、今回はリアクションのお芝居が多いですよね。
ほぼ100%リアクションと言っても過言ではないくらい、受け身ですね。そういうところも、おしゃべりに見えない理由かなと思います。
――今回は下北沢オールロケで、実在のスポットも多数登場します。こうした“場”から役を作っていった部分はありますか?
役者はよく「今回の役は役作りで云々」と言いますが、僕自身の感覚だけで言うと役者ができることって実は少ない。メイクやスタイリスト、監督、照明、撮影、録音というスタッフたちがそういう状況にさせてくれているのがすごく大きいと思うんです。今回も、僕自身というよりスタッフィングが素晴らしかったんですよね。
下北沢という街自体もすごく寛容で、物理的に「ここでロケしていいよ」というものというよりも、街自体がどんな人も拒絶しない感じがありました。下北沢って、バンドマンや役者に憧れを持って上京した人たちが住む、といった部分があるじゃないですか。その後夢半ばにして挫折して実家に帰る人もいるし、ちょっと成功して別の場所に移り住む人もいて、街全体が交差点のように人が入れ代わり立ち代わり“廻る”という側面を持っているからこそ、受け入れる力を持っているんでしょうね。
――自分は地方出身で「下北沢=お洒落」という意識や街自体に憧れがありましたが、東京生まれの若葉さんはいかがですか?
僕はあまりその意識はなかったですね。十代の時は高円寺を中心に阿佐ヶ谷や荻窪あたりでいつも遊んでいたので、もし高円寺が舞台だったら思い出があるぶん、青というキャラクターの温度が高くなっていたかもしれません。下北沢に対してそんなに思い出がないぶん、あの温度でいられた気はしています。

――これだけ生活感がある、現実と密接した作品だと、撮影中の役者の手ごたえはどういうところにあるのでしょう?
手ごたえはないですね(笑)。ただ、その「居心地の悪さ」は本作に限らずいつも感じていたいし、どの現場でも不安な状態でいたいという意識があります。
役者って、号泣したり怒鳴ったり絶叫したり、そういった派手なことをして悦に入る生き物だと僕は思うんです。気持ちいいことが好きなんですよね。ただ僕自身はそういったことに興味を持てなくて、映画館で作品を観ていても冷めちゃうところがあるから、そういうものにはしたくなかった。だから、手ごたえのなさがある種の正解でしたね。
――となると、本作の自主映画の撮影シーンは、結構ご自身に近い……?
居心地の悪さは、あんな感じに近いですね(笑)。映画に出てきたように、演技をした後でスタッフが集まって相談している……みたいなことはよくあります。
スタッフも監督もキャストも作品ごとに違うから、慣れることが本来だったらありえないはずなんだけど、どうしても場数を踏むと「こなす」ようになったり発言権を持ってしまったり、やればやるほど役者自体が面白くなくなっていく、ということをすごく感じているんです。だからこそ、常に「何者でもない」という気持ちでいたいですね。
――ただ、冒頭におっしゃっていた「面白そうな企画を動かす」は、経験を積んだからこそスムーズにいくところもありますよね、きっと。
そうですね。ただ、極論をいうと僕が関わらなくてもいいんです。単純に僕が観客として観たいと思うものを自分なりのアンテナで見つけてきたり、「この原作が面白いよ」ってプロデューサーに声をかけたり、そういうことをしていきたいなと思っています。
――ということは、まだ「観たい映画」は足りていないという感覚ですか?
というよりも、僕自身がバウスシアター(吉祥寺のミニシアター。2014年に閉館)などに通っていた十代のころから、興味のある映画しか観ていなかったんですよ。映画を知りたくてたくさん観るのではなく、自分が興味あるものを観るために劇場に足を運んで、Tシャツやポスターを買っていました。
自分の作品の選び方も、「十代のときの自分が興味を持てるか」が大きくて、そういったものが世に出てきて受け入れられたらいいなという思いはありますね。
――なるほど。『街の上で』はまさに、十代の映画好きの方々が「お洒落そうだから観てみたい」と思える作品だと感じました。
自分も十代のころ、「この映画を観ている自分がカッコいい」というような理由でフランス映画を観て、内容は全然わからないのに優越感に浸っていました(笑)。でも、きっかけは何でもいいと思うんです。
ノリで観に行ったけど、「明日だけ頑張ってみようかな」と思えるようなものを作りたいですね。別に「人生観が変わってください」というほどじゃなく、ささやかなものでいい。そういう意味では、自分に向けて作っている感覚もあるかもしれないですね。
――本作を拝見して、読書家が多いのも下北沢という街を象徴しているように感じました。先ほど話題に上ったように、若葉さんご自身も多くの本に触れている印象がありますが、どういったものがお好きですか? 漫画なども読まれますか?
漫画は、最近の作品はあまり読んでいないのでわからないんですよ。十代の頃に赤塚不二夫さんやいがらしみきおさん、山田花子さんたちの作品を読み漁っていて、自分の芝居のテンポ感やリズムはそこからすごく影響を受けています。
小説は文学やノンフィクションも読みますが、人間の深層心理に触れているものが好きですね。最近だと、青山真治監督の小説版「ユリイカ EUREKA」を読み返しました。当時は訳も分からず読んでいたのですが、改めて読み返すと自分自身に突き刺さる言葉があり、背筋が伸びる気持ちにもなりましたね。
――感性を高める一環として、読書を行っているのでしょうか。
自分の感性には限界値があると思うので、高めようというよりも「自分が言語化できなかったものを言語化してくれている方々がいて、それが字面になっている」というところに面白みを感じますね。言葉のチョイスや作家が書いた想いに共鳴したり、あるいは否定的に感じたり……。ワード一つひとつを粒立てて感じさせてもらっています。
――お話を伺ってきて、「興味」が若葉さんの原動力のひとつなのかな、と感じました。
そうですね。たとえば『AWAKE』だったら山田篤宏監督の初長編というところにすごく興味があって参加したいと思いましたし、「おちょやん」は役者の話という企画自体が面白くて、杉咲花さんに対する興味もありました。大作だろうが自主映画だろうが、選び方はあまりブレていなくて、「自分が参加したい」とアンテナが反応するものに出ていますね。
――キャストのお話でいうと『愛がなんだ』『街の上で』『くれなずめ』「おちょやん」と、成田凌さんとは共演作も多いですが、若葉さんにとってどんな存在ですか?
作品としてはいっぱいやっているんですが、がっつり目を合わせて共演したのは『くれなずめ』以降なんですよね。あれはすごく面白かったです。
成田くんに対しては、勝手に「斜に構えてる人なのかな?」という印象を抱いていたのですが、実際に喋ってみるとずば抜けてピュアな人でした。思ったことを何でも言っちゃうから勘違いされてしまうこともあるだろうけど、八方美人よりはよっぽど信頼できるし、彼の映画に対する姿勢は、役者としてリスペクトできるなと思います。
――今泉監督作品だと、同じく常連である芹澤興人さんとの共演シーンも印象的でした。あの部分、「街が変わっていく」という本作の裏テーマを描いていますよね。『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』や『わたしは光をにぎっている』『ノマドランド』など、自分の生活圏が消える、変化する哀しみを描いた作品が世界規模で増えている印象があるのですが、若葉さんはどう捉えていますか?
その感覚はすごく分かります。大きな事柄をやらないほうが、実は世界が広がっていく気がしますね。たとえば、阪本順治監督の『顔』はミニマムな世界でミニマムな人間のやり取りを描きながら、そこに様々な人の人生が混じりあっていって、対岸の火事ではないことを見せつける。赤堀雅秋さんの作品も、ミニマムな人間関係で世界を描いている。
今泉さんの作品にも同じことを感じていて、飲み屋で飲んだくれたおっさんが実は真理を突いたことを言って、その時代のその世界が見えてくる。たとえば戦争をテーマにした作品をストレートにやるのも良いのですが、それだと対岸の火事のように思ってしまう人も出てくる。それよりも、人間がそこに生きて、暮らして、ものを食べて恋愛をしてつながっていく、ということをやるほうが、実は世界を広く描けるんじゃないかという意識はありますし、そこにとてつもない魅力を感じているのは事実です。
――若葉さんの中で、『葛城事件』(赤堀雅秋監督作)と『街の上で』が根っこでつながっている、というのは非常に面白いです。
つながっていますね。それと、いまお話しした『顔』や、『アイデン&ティティ』『リアリズムの宿』もそう。ああいった映画に参加したいと思って、ここにいるという意識はあります。ゼロ年代の映画に色濃く影響を受けて、憧れを抱いています。
――個人的には、若葉さんは着実にその道を歩んでいる印象があります。『街の上で』の中にも、『愛がなんだ』と山下敦弘監督の『苦役列車』のチラシがお店に飾ってあるシーンがありましたし。
それだと嬉しいなという気持ちはありつつ、それじゃあ食えないよ、っていう気持ちもあるから難しいですね(苦笑)。
――以前、西川美和監督にゼロ年代の映画のお話を伺った際に、同じことをおっしゃっていました。「それでもやる」作り手が、当時踏ん張っていたと。
当時はまだぎりぎり35ミリフィルムで撮れていたこともあって、画の作り方にもうちょっと色気がありましたよね。もちろんデジタルの良さもありますが、逆に言うと「誰でも撮れてしまう」という現状もあって、そこがどうなのかなという思いは個人的にはあります。
――ただ、それでいうと『街の上で』には、下北沢の空気感がしっかりととじ込められているのではないかと思います。あの頃を思い出せる作品でもありました。
そうですね。何回も観たくなる映画が僕は好きなので、そういう作品にしたいなという意識を持って作りました。10代の頃の自分が真っ先に観に行く映画になったんじゃないでしょうか(笑)。
文/SYO
【若葉竜也 プロフィール】 1989年6月10日生まれ。東京都出身。作品によって違った表情を見せる幅広い演技力で数多くの作品に出演。赤堀雅秋監督作『葛城事件』(2016)の葛城稔役で、第8回TAMA映画賞最優秀新進男優賞を受賞。主な出演作に、映画『愛がなんだ』(2019)、『台風家族』(2019)、『ワンダーウォール 劇場版』(2020)、『生きちゃった』(2020)、『朝が来る』(2020)、『罪の声』(2020)、『AWAKE』(2020)、『あの頃。』(2021)など多数。NHK連続テレビ小説「おちょやん」で朝ドラ初出演。成田凌、高良健吾らと共演する『くれなずめ』が、2021年4月29日公開予定。
『街の上で』
4月9日(金)より、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開
監督・脚本:今泉力哉
脚本:大橋裕之
音楽:入江陽
主題歌:ラッキーオールドサン「街の人」
出演:若葉竜也 穂志もえか 古川琴音 萩原みのり 中田青渚 村上由規乃 遠藤雄斗 上のしおり カレン 柴崎佳佑 マヒトゥ・ザ・ピーポー(GEZAN) 左近洋一郎(ルノアール兄弟) 小竹原晋 廣瀬祐樹 芹澤興人 春原愛良 未羽 前原瑞樹 タカハシシンノスケ 倉悠貴 岡田和也 中尾有伽 五頭岳夫 渡辺紘文 成田凌
配給:「街の上で」フィルムパートナーズ
【ストーリー】 下北沢の古着屋で働いている荒川青(若葉竜也)。青は基本的にひとりで行動している。たまにライブを見たり、行きつけの古本屋や飲み屋に行ったり。口数が多くもなく、少なくもなく。ただ生活圏は異常に狭いし、行動範囲も下北沢を出ない。事足りてしまうから。そんな青の日常生活に、ふと訪れる「自主映画への出演依頼」という非日常、また、いざ出演することになるまでの流れと、出てみたものの、それで何が変わったのかわからない数日間、またその過程で青が出会う女性たちを描いた物語。
©「街の上で」フィルムパートナーズ 撮影/西邑匡弘 スタイリング/TOSHIO TAKEDA(MILD) ヘアメイク/FUJIU JIMI