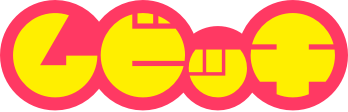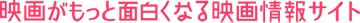人気ドラマ「カルテット」の脚本家・坂元裕二と土井裕泰監督が、映画で初タッグ。主演は菅田将暉と有村架純。2015年から2020年にかけて、5年間に及ぶ恋の行方を描く――。1月29日より劇場公開されている『花束みたいな恋をした』は、座組の時点で傑作の予感漂う作品だった。

しかも、本企画は菅田と有村への「当て書き(キャストを想定して脚本を執筆すること)」。菅田は「問題のあるレストラン」、有村は「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」で坂元作品を経験しており、さらに当て書きとなれば、ファンの期待も高まるというもの。ちなみに菅田と有村が過去に共演した映画『何者』は群像劇で、シーンはそこまで重なっていない。そのため、今回が待望の本格共演といえる。
「カルテット」の黄金コンビが映画で観られるという喜び、菅田と有村という同世代の俳優のトップランナーが恋人役としてがっつり組む興味。スタッフ・キャスト共に「外さない」人選といえる『花束みたいな恋をした』。しかしてその中身は、それぞれの個性が百花繚乱に咲き乱れる、花束のように彩り豊かな作品となった。

観た者の思い出を呼び覚ます「ウソがない」物語
東京・京王線の明大駅前で、終電を逃してしまった大学生・麦(菅田将暉)と絹(有村架純)。初対面のふたりは、始発までの時間を飲み屋で過ごしながら、互いの趣味の話に花を咲かせる。イヤホンコードが絡まる話、天竺鼠のライブに行き損ねた話、好きな作家や音楽、映画……。趣味も価値観もぴったりハマったふたりはあっという間に恋に落ち、ほどなくして同棲を始める。だが、麦が就職し、生活リズムが合わなくなったことから、気持ちのズレが生じ始め……。
『花束みたいな恋をした』の魅力は、一言で表すなら「あの頃の自分が、そこにいる」ところだろう。恋愛、バイト、就活、就職に同棲……。麦と絹が経験する出来事の一つひとつや、そのときに生まれる感情が繊細に紡がれていくなかで、私たちが20代の間に経験した個々の思い出と結びつく。
或いは、10代でこの作品を観たならば、自分に待ち受けている直近の未来を思うのではないか。映画を観て、共感すると同時に、脳内で「自分事」に変換されていくかけがえのない体験――。しかもその“純度”が非常に高いため、観た者にとって「忘れられない映画」になるのだ。
電車に「乗る」ではなく「揺られる」と表現する相手の言葉に惹かれ、好意へと変わっていく過程も、「ポイントだったらとっくに貯まってる」という恋心が募る描写も、就活で心身が疲弊する姿、同棲直後の絶頂と倦怠感、ケンカの際に口をついて出てしまった言葉も……。細部こそ違えど、私たちが見聞きしたこと、実際に経験したこととシンクロする。『花束みたいな恋をした』には、徹頭徹尾ウソがない。だからこそ、愛せるし信じられる。

ここには大きく分けて、3つの要因があるように思う。それは、「坂元裕二が紡ぐ真実味」「土井裕泰監督が撮る実時間」「菅田将暉&有村架純が醸す生活感」だ。手練れのスタッフ・キャストの実力と感性が有機的に作用した、驚くべき完成度。ここからは、その3点に絞って本作を分析していこう。

私たちの心の中にある感情を言語化する天才・坂元裕二
まずは、坂元による珠玉のセリフ。彼の魅力は、あくまで私見だが「言語化できない心情を言語化してみせる」部分にあるように感じる。
1つは、私たちが日常の些細な瞬間に感じて、だけれどもどこにシェアするでもなく放置したもの。たとえば「月5万8000円のアパートの郵便受けに入っている3億2000万円の分譲マンションのチラシ」に思わず笑ってしまうことも、「新しいセーターをおろした日に焼き肉屋に連れて行かれた」ことへのモヤモヤも、「あるある」ではないだろうか。坂元は、これまでの作品でも見過ごされがちな些末な出来事を丁寧に拾ってきたが、観る者に「わかる!」と共感させる能力が突出している。
そして、リアルではなく「リアリティ」をまとった言葉のチョイス。就活中の麦と絹が絞り出す「普通になるのって難しい」というモノローグ、ふたりがケンカした際の「好きで一緒にいるのに、何でお金ばっかりになるんだろって」という本音、売れようともがくクリエイターが語る「協調性とか社会性って、才能の敵だからさ」という言葉……。日常で実際に発することはなくても、言いたいと願っている語句がちりばめられている。本作の主軸はラブストーリーだが、「Mother」や「Woman」を手がけた坂元らしい“痛み”が、しっかりと根付いているのだ。

実時間を感じさせる描写を巧みに盛り込んだ土井裕泰監督
土井監督は、「カルテット」や「逃げるは恥だが役に立つ」、『罪の声』など、多くのヒット作を世に送り出してきた人物。だが、一言で表すならば彼は作品に徹底的に尽くすタイプだ。どんなテイストの作品であっても堅実に、かつ愛情をこめて演出する。
職人的な、チューニングのうまさが光る土井監督。本作では、終電後の明大駅前から調布駅まで歩いていく道のり、同棲を始めた麦と絹が家までの徒歩30分間を楽しむ過程等々、実時間を感じさせる描写を丁寧に行い、観客に静かな「体験」を促す。我々が生きる日常に根差した時間の描き方をしているからこそ、現実と接地面の多い物語に仕上がっている。決して主張は強くないが、こうした細やかな気配りが、作品と観客の間からノイズを取り去っている。
また「いまを生きる麦と絹をただ、見つめる」を自身のスタンスにしていたというエピソードが興味深い。作為的な演出は極力排し、菅田と有村の演技を丁寧に掬い取っていくこと。ふたりのパフォーマンスを積み上げていくことが、嘘のない物語を形成していく――。これは、役者にとっては重責であると同時に、最大級の誉れといえるのではないか。よほどの信頼がなければ、この結論には達せないだろう。

役を自然に“見せる”手練れ、菅田将暉&有村架純
当て書きした坂元と、託した土井監督。ふたりからバトンを受け取り、正真正銘「役を生きた」菅田将暉と有村架純。ふたりの自然体な演技は、ただ淡々とセリフを発しているだけでなく、経験と感受性に裏打ちされた、非常にテクニカルなものだと言えるだろう。
というのも、本作はかなりの分量がモノローグに割かれており、現場で演技をする際はそれがない状態。さらに前述したように、坂元が紡ぐセリフは独特の文体のため、技量が追い付いていなければ言葉に引っ張られ過ぎてしまう危険性もはらんでいる。菅田と有村が共に坂元作品を経験済みで、そして何より表現力がずば抜けているからこそ、自然に“見える”のだ。
特に後半、ふたりがぶつかり合い、涙をはらはらとこぼすシーンは圧巻。それぞれに泣きの演技の表出方法が異なっているのも、凄みを感じさせる。役どころを見事に演じ切っているのは勿論だが、観客がスムーズに自己投影できる“器”としても機能しているのは、流石としか言いようがない。私たちと同じ目線や価値基準を持っている人間を、的確に組み立てている。ちなみに、菅田と有村はともに1993年生まれ。出身地もデビュー時期も近く、共鳴する部分も多かったのではないだろうか。

『花束みたいな恋をした』は布陣の時点で最高級の作品だが、実力者をただ集めただけでは、良い映画にはなっても、忘れられない傑作までは到達できない。彼らが互いを理解し、そのうえでベストパフォーマンスを発揮したからこそ、本作は彩り豊かな“花束みたいな映画”になった。そして、彼らが投げた花束を受け取るのは、他ならぬ私たちなのだ。
文/SYO

『花束みたいな恋をした』
2021年1月29日(金)より、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開
監督:土井裕泰
脚本:坂元裕二
出演:菅田将暉 有村架純 清原果耶 細田佳央太 韓英恵 中崎敏 小久保寿人 瀧内公美 森優作 古川琴音 篠原悠伸 八木アリサ 押井守 Awesome City Club PORIN 佐藤寛太 岡部たかし 萩原みのり 福山翔大 萩原利久 片山友希 宇野祥平 佐藤玲 水澤紳吾 オダギリジョー 戸田恵子 岩松了 小林薫
配給:東京テアトル リトルモア
【ストーリー】 東京・京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った大学生の山音麦(菅田将暉)と八谷絹(有村架純)。好きな音楽や映画がほとんど同じで、あっという間に恋に落ちた麦と絹は、大学を卒業してフリーターをしながら同棲を始める。拾った猫に二人で名前をつけて、渋谷パルコが閉店してもスマスマが最終回を迎えても、日々の現状維持を目標に二人は就職活動を続けるが…。
©️2021『花束みたいな恋をした』製作委員会