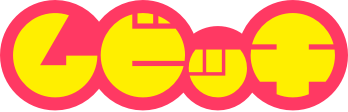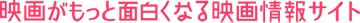MC:ありがとうございます。それでは、いくつか質問をさせていただきたいと思うんですけれども、『リバーズ・エッジ』は1993年に連載がスタートして94年と続いていった伝説的な作品であると、ご挨拶のなかでも端々にご紹介いただきました。監督、もう少し補足をいただきたいのですが、「2018年の今、なぜ『リバーズ・エッジ』を?」ということをどうとらえていらっしゃいますか?
行定:そうですよね。僕自身も「今なぜ?」って正直思いました(笑)。僕からの発案というよりは、二階堂ふみからの発案だったんですね。「岡崎京子の『リバーズ・エッジ』って興味あります?」っていう一言から始まったんですけど、興味がないわけがないですよね。僕が(監督を)やるともなんとも答えてないですよ。僕が「興味があるよ」って言ったら、「OK。じゃあ話しましょう」からスタートしたんですね。それで、その時考えたのは「なぜ今『リバーズ・エッジ』なんだ」と。プロデューサーともいろいろ話したんですけど、まずそこですよね。いろいろ考えて、でも二階堂はそのころは21くらい?
二階堂:20歳のときだったと思います。
行定:20歳だったかな。20歳の時だったんですけど、彼女が何で『リバーズ・エッジ』にこんなに狂信しているのか、刺さっているんだということを感じるんですよね。よくよく考えてみると、1994年の翌年にオウム真理教の地下鉄サリン事件が起こったり、震災が起こったりするわけですね。それで、この映画の中のキーワードにもなっている“平坦な戦場を生き延びる”という、それを長年僕らはいろんな局面で生き延びてきたんだろうなと。そう考えてみると、今だってこの世の中はどうなっていくかわからない、淵に立たされているようだなと。映画を作ってみてわかったのが『リバーズ・エッジ』、その“リバーズ”っていろんな川がありますけど、川の流れって一つの歴史で、いろんな岸があってそこに少年少女たちがいつも佇んで川の流れを踏ん張って見ながら生きている、その“生きる”というテーマが一つ見えてきた、そうなったときに、これが如実に剥き出しになった『リバーズ・エッジ』という漫画が当時描かれていて、それが今の人に刺さるんじゃないかと。どんな時代にもこの普遍的なテーマはたぶん刺さり続けるだろうと、だったらこれをあえてやるというのは今かなと僕は思ってこれに飛び込みました。
MC:二階堂さんの「興味がありますか?」という質問、これから始まったわけですけれども、二階堂さんは主人公たちと同じ16歳のときに初めて原作をお読みになったそうですね。
二階堂:そうですね。誕生日を迎える17歳というタイミングの高校2年生のときだったんですけど、ちょうど『ヒミズ』という映画を撮っていたときに、美術部のスタッフの方が「これ、好きだと思う」というふうに貸してくださって、それで初めて岡崎先生の『リバーズ・エッジ』という作品に出会ったんです。その時自分が抱えていたものがそのままその作品の中にあって、でもその時はそんなに映画にしたいという気持ちよりかは、まずその衝撃がすごく強くて、自分の中に傷跡が残ったような感覚だったんですけど。その半年後くらいにちょうど企画が立ち上がったので、今日こういうふうに皆さんの前にお披露目するまでには、実は6年半、7年ぐらいかかったんです。でも、こういう若い人たちが抱えるものであったりとか、その時に感じていることとか生きることみたいなものを、10代後半というのは特に疑問に思ったりとか、考え始めたり気づき始めたりする頃だと思うんですけど、それは行定監督がおっしゃっていたように、普遍的なテーマだなと思うので、ぜひここに来ていただいている皆さんたちにも映画を観て感じていただけたらいいなと思います。
MC:今のお話を聞いて、『ヒミズ』の美術部のスタッフの方に本当に感謝したいなと思いますね(笑)。
二階堂:本当にそう思います(笑)。
MC:そこで手渡すことがなかったら、もしかしたらこの日はなかったかもしれないということですからね。おもしろいものですよね。
キャストの皆さんにお集まりいただきました。それぞれに青春をどう生きていけばいいのかという淀みの中で、ある種の悩みを抱えているキャラクターが出てきますが、おひと方ずつ伺っていきたいと思います。補足があれば皆さんに参加していただきたいのですけれども、まず吉沢さんに伺います。山田というキャラクター、いじめられていますし、しかもいじめといっても生半可ないじめじゃない。
吉沢:そうですね。
MC:そしてゲイであるということを自分から公言することはなく、流れの中でという感じですが、これまでの経験を踏まえてこの難しい役どころの役作りはどうでしたか?
吉沢:外見的な部分でもやっぱり細い男だなというイメージはあったので、筋トレするとかじゃなくて走ったりとか、ちょっと食事も抑えたりもしましたけど、やっぱり一番は原作と台本を行き来して、ひたすら人間性を考えるということをやっていて。漫画原作なんですけど、すごく余白の多い作品というか、自分の考えで埋めなきゃいけない部分もすごくありましたし、掘り下げれば掘り下げるほど底が見えなくなってくるというか。現場のときもずっと悩んでいたんですけど、すごくおもしろい男で、一見、ゲイだったりいじめられていたりということで社会を斜めに見ているといいますか、そういう部分って、死体に安心感を求めている山田と、トオルという女子も男子もみんな好きになりそうなスポーツマンみたいな、誰もが憧れを持つ男が好きだという部分と、すごく変ないろんな矛盾を読んでいて感じて、そういう部分をどうやって描けばいいかなということをひたすら考えながら、後は周りの、それこそハルナとか観音崎とかに対する思いとか、いろいろなことを考えながらやっていましたね。