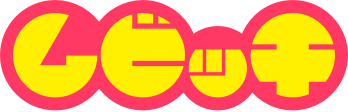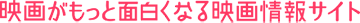第70回カンヌ国際映画祭においてグランプリを受賞した、ロバン・カンピヨ監督最新作『BPM ビート・パー・ミニット』が3月24日より公開となる。本作の日本公開に先立ち、2月28日にアンスティチュ・フランセにてトークイベントが開催され、映画批評家の大寺眞輔が登壇した。

エイズ患者やHIV感染者への差別や不当な扱いに対して抗議活動を行う団体ACT UPのメンバーだったというロバン・カンピヨ監督自身の経験をベースにした本作。カンピヨ監督は、本国フランスでは一躍「時の人」となっており、映画監督としてだけではなく活動家・文化人として注目されている。イベントでは、フランスの映画事情に詳しい大寺が、本作とカンピヨ監督の魅力についてたっぷりと語った。
大寺眞輔によるトーク レポート
■タイトルの意味とは?
まず最初に、この映画のタイトルである「BPM」とは何か?それは心拍数や音楽のテンポ表す言葉です。人間が運動などをしていて自分の鼓動を自覚し始めるのが120くらいからと言われています。また120はポップ・ミュージック、ハウス・ミュージックなどのスタンダードなテンポとも言われています。そういった人間の生理的状況と音楽の隠喩とのダブルの意味を兼ねたタイトルなのです。
■エイズの感染拡大により、映画界から遠ざかったカンピヨ監督の過去
本作には3つの柱があります。エイズに対する恐怖を描いていること、エイズに対するサポートを行っている団体ACT UP PARISの活動を追った映画であること、そして主人公ショーンとナタンの二人の愛情と別れです。最初の二つはカンピヨ監督の個人的経験や80~90年代の時代背景を深く反映しています。
エイズが世に知られ始めたのは、カンピヨ監督が20歳やそこらのハイティーンの頃でした。雑誌「リベラシオン」で初めてエイズ患者の有名な写真(本編にも登場)を観た時には恐怖のあまり、しばらく同性の恋人とセックスできなくなってしまったとのこと。これはまさに本編に登場するナタンと同じ状況ですね。ナタンとのシーンは監督自身の思い出が基になっていると言えます。1983年にIDHEC(現ラ・フェミス/フランス国立映像音響芸術学院)に入学し、ローラン・カンテ監督(『パリ20区、僕たちのクラス』)と出会いますが、卒業後すぐに映画の職に就くことはありませんでした。1992年に、自分がやはりエイズに対して立ち上がらなければならないと思い、ACT UPに参加。10年の紆余曲折を経て行動を起こした彼は決してエリートコースでもないし、監督として多作でもない。しかし、こういった経験が後々映画のキャリアにも有益に繋がっていくのです。インタビューで彼は「エイズの感染拡大が私を映画から遠ざけました。私はACT UPに参加しました。そこはとても幸福感に満ちた自由な場所でした。人々は同性愛に対する無関心と闘っていました」と語っています。
■“非トレンド”と言われたなかで、絶大な評価を勝ち取ったその実力とは?
私はロメールやゴダールの映画が好きですが、彼らの映画には同性愛があまり登場しません。この病気は映画にとっても難題な病気です。ラブシーンにコンドームをつければ一気に雰囲気が壊れてしまうからです。けれど、カンピヨ監督はそのヌーヴェルバーグに描かれない新しい要素を描くことが、自分の主義主張にとても重要であると気づき、また現代の使命でもあると思ったのです。
カンピヨ監督は本国でどんな評価をされているのでしょうか?前出のように、ヌーヴェルバーグの直系でありながら、ダルデンヌ兄弟ともよく比較をされる、ナチュラリズム(自然主義)系譜に属する監督です。最近この手のナチュラリズム系の監督は、フランスでの映画批評の流れ的に「トレンドじゃない」と言われ冷遇されることもしばしば。しかしカンピヨ監督の場合は別で、『BPM ビート・パー・ミニット』は昨年のインディーズ系の映画ではフランス最大のヒット作となり、映画祭でも高評価で賞を取りまくり、メジャー感と作家性を兼ね備えた稀有な存在と言われています。
■描きたかったのは、「病気」よりも「孤独」
カンピヨ監督の特徴として、例えばデモのシーンを描く時でも、デモそのものよりその前後、特に後を描くことが挙げられ、「行動をめぐるディスカッションの映画」であると言えます。これは、観ている者にも様々な登場人物の考えを見て自分はどうだろうと考えさせられる構造です。本作で後半の二人の別れは悲劇だけれど、個人の悲劇と思い出を描くことで終わってしまうのではなく、個人の死とACT UPの活動を同じ比重で描く。ショーンの死は重い現実だけれども、だからこそ闘争を継続していかなければならない、その思いを込めて二つの層を描いているのです。
「映画の最後では、ショーンが死のトンネルの中にいるように私は描きたかったのです。彼は完全な孤独の中にいて、誰もそこに届かないような状態。そこで描きたかったのは病気よりも孤独でした。このシナリオを書き終える数ヶ月前に私の母が亡くなったのですが、その経験はこの時代に私の知っていた友人たちのことを思い出させもしました。彼らはまるでトンネルの中にいるか、想像もできない別の場所、生よりも死に近い場所にいる。彼が病気のせいで孤独になっていく、それを描きたい。同時に参加できなかったグループの活動も描きたいのです」とカンピヨ監督は語っています。
■『アデル、ブルーは熱い色』と真逆!?セックスシーンの荒々しさが醸し出すリアル
カンピヨ監督は、ドキュメンタリーの巨匠ワイズマンにシンパシーを感じるとよく言っています。ワイズマンの作品からはナチュラリズムや現実に対するアプローチがよく見えるそうです、以下、カンピヨ監督の言葉です。
「フレデリック・ワイズマンの作品は、現実に対してとてもエモーショナルだと思う。彼の映画では全ての人々が完全に平等であるかのように感じられる。私の映画はしばしばダルデンヌ兄弟に比べられるがそれはあまり同意できない。それよりワイズマンにシンパシーを感じる。例えばセックスシーンもあまり準備を行わずに、意図的な荒っぽさを取り入れる。撮影時間も短いし、決して無理なことはさせない」
これは、例えば同じ同性愛のセックスを描いた『アデル、ブルーは熱い色』と際立って違うところです。ロマンチックな部分を意図的に削ぎ落としています。言ってみれば、それは本当のセックスシーンに実は近いのです。また、本作のクラブのシーンで映し出される「塵」は、カメラが寄って行くとまるでHIVウィルスのように見えます。この塵はCGではありませんが、とても効果的だと思います。顕微鏡的な視界にまで映画が移行しているような、幻想的でポエティックな場面。カンピヨ監督はこう語ります。「私たちはただスポットライトを当てただけなのです。それが魔法のような映像になった。偶然発見した。色々な世界が並行して存在していることを見せたかったのです。病気によって孤独になってしまった。孤独や悲劇がありつつ、同時にそうじゃない世界、活動家の集会、クラブでダンス、世界は続いていくということを…」

『BPM ビート・パー・ミニット』
3月24日(土)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、ユーロスペース他にて全国ロードショー
脚本・監督:ロバン・カンピヨ
出演:ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート アルノー・ヴァロワ アデル・エネル
配給:ファントム・フィルム
【ストーリー】 1990年代初めのパリ。エイズの治療はまだ発展途上で、誤った知識や偏見をもたれていた。「ACT UP Paris」のメンバーたちは、新薬の研究成果を出し渋る製薬会社への襲撃や高校の教室に侵入し、コンドームの使用を訴えたり、ゲイ・プライド・パレードへ参加するなどの活動を通し、エイズ患者やHIV感染者への差別や不当な扱いに対して抗議活動を行っていた。行動派のメンバーであるショーンは、HIV陰性だが活動に参加し始めたナタンと恋に落ちる。しかし、徐々にショーンはエイズの症状が顕在化し、次第にACT UPのリーダー・チボーやメンバーたちに対して批判的な態度を取り始めていく。そんなショーンをナタンは献身的に介護するが…。
© Céline Nieszawer