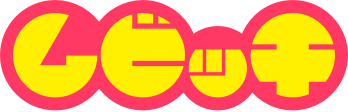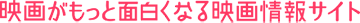日本を代表する名優・山﨑努が「僕のアイドル」(「柔らかな犀の角」山﨑努著・文春文庫より)と敬愛する画家・熊谷守一(通称モリ)を演じた映画『モリのいる場所』が2018年に公開されることが決定した。
企画の始まりは2011年。山﨑が『キツツキと雨』の撮影現場で、監督の沖田修一に「こんな面白い、興味深い画家がいるよ」と熊谷守一を紹介したことがきっかけ。日本映画黄金時代を体現する名優からのヒントに、現在の日本映画をリードする俊英監督が刺激を受け、それから6年。沖田監督が山﨑努=熊谷守一を念頭に、ユーモラスで温かなオリジナルストーリーを作り上げた。
山﨑努は、『天国と地獄』(63年/黒澤明監督)の犯人役でセンセーションを巻き起こし、『赤ひげ』(65年)『姿三四郎』(65年)『影武者』(80年)の黒澤作品や、『お葬式』(84年)『タンポポ』(85年)『マルサの女』(87年)など伊丹十三監督作品をはじめ、数々の名作における重厚な演技で唯一無二の存在感を放つ名優。主演は『死に花』(04年/犬童一心監督)から13年、単独主演は『刑務所の中』(02年/崔洋一監督)以来15年ぶりとなる。その名優が映画化を待望した人物は、自宅の庭でひたすら虫や鳥、草花を見つめ続け、「仙人」と呼ばれた画家モリ。
写真は、長年丹精込めて作った庭で蟻の行列を観察するモリ(山﨑努)。その汚れない瞳はどこまでもピュアで愛らしい。これまであまり目にしたことがないこのカットからも、本作品におけるモリ=山﨑努が従来のイメージを大きく裏切る、新境地であることが伺える。
昭和の大スター豪華共演のTVドラマ「やすらぎの郷」(EX、9月29日フィナーレ)の高視聴率、佐藤愛子著のエッセイ「九十歳。何がめでたい」(小学館)がベストセラー入りするなど、魅力的な高齢者の活躍によってアラハンブームが巻き起こっている昨今。名優・山﨑努、13年ぶりの主演で満を持して“R100(アラハン)生涯現役画家”役に挑戦、老境にてさらに輝きを増す。
山﨑努コメント
「熊谷守一について」
古い簡素な木造家屋を背景に、仙人のような白い立派なひげを生やした老人が、両手の杖にすがってかろうじて立っている写真。しかめっ面。和服、下駄履き。
藤森武写真集『獨樂 熊谷守一の世界』のなかの一点で、老人はもちろん熊谷守一画伯。当時94歳。キャプションに「45年、この家から動きません。この正門から外へも、ここ30年、出たことがないんです。でも8年ぐらい前、一度だけ垣根づたいに勝手口まで散歩したんです。あとにも先にもそれ一度きりです」とある。これにはびっくり、思わず笑ってしまった。僕も出不精のほうなので共感の笑いだったかもしれない。それにしても30年とは尋常ではない。
「蟻は左の二番目の足から歩き出す」のだそうだ。モリカズさんの画文集『虫時雨』で読んだ。「この間カニをもらったので歩き方をずっと調べてみましたが」「どの足から歩き出すのか、いくら見てもわからず閉口しました。カニの絵がいまだに描けないのはこのためなんです」と続く。
カニも蟻も草も木も石も空も、彼はじっと見る。いつまでも見る。そんなモリカズさんの様には圧倒されてしまうのだが、同時にその語り口には何ともいえない愛嬌があって、そのせいか、熊谷さんというよりもモリカズさんと呼びかけたくなってしまう。つい、そうなってしまう。つまり僕は彼の人柄に惚れている。
「熊谷守一を演じて」
去年(2016年)の秋、突然沖田監督から、モリカズ役をやってみないか、との依頼があった。――配役はいつも突然であって、その突然が俳優業の楽しみでもある。僕はこれまで、この役をやりたい、と手を上げたことは一度もない。役を振るのは監督やプロデューサーの役目で俳優のすることではない。僕は、天命のようにある日突然、役を与えられるのを待つ。そしてその決められた役の枠の中でどう生きるのかを工夫する。それが自分の仕事だと思っている。
正直、今回の役作りは非常に大変だった。自伝、画文集等からキャラクターは理解している。写真も豊富にあって容貌も充分確認した。だがその姿がいきいきと動きを出してくれないのだ。とくに顔の表情。惚れている人、敬愛する大切な人を演じることがいかに難しいか、関西弁で呟けば「難儀やなあ、あかん」。
苦肉の策として、モリカズさんに仮面を被せることにした。内面と外界を隔てる仮面。いつでもどこでもその面をつければモリカズとして通る符丁のようなお面。
さて、どんな面にするか。
写真集『獨樂』を何度も繰って表情をチェック。惚けたような、放心したような顔がある。同席の人たちやその状況とは全く関わらない、まさに仮面。しかしこの面相は残念ながら僕にはまだ無理だ。かすかに眉間にシワをよせた渋面も多い。穏やかな微笑もある。藤森さんは微笑の面を表紙に掲げている。チャーミングな肖像。
僕は渋面を僕のモリカズの仮面に選んだ。夫人の秀子さんの「大事に思うことがあまりに人と違っているので、一応のおつき合いで、それ以上のふれ合いには(家族も含めて)なりにくいと思います」(『蒼蠅』)というモリカズ像を強調したかったから。
通常の演技は、表情の豊かさを目指すが、この映画では逆に表情の変化を殺すことにしたわけだ。なかなか厄介な、そして不安な試みだった。かくなる上は声のニュアンスも殺してしまえと、フラットなかすれた老人声にした。これは多少ヤケ気味。撮影の現場には何が起きるか予測不能の面白さがある。設計した仮面がどこかで外れてしまうことも秘かに期待していた。今、これを書いている時点で、僕はまだ撮られた映像を見ていない。依然不安は残っている。
「沖田修一監督について」
沖田修一さんは「場所」にこだわる監督のようだ。『南極料理人』の南極、『キツツキと雨』の木曽山奥の寒村、今度の『モリのいる場所』では関東の庭。東北でも、九州、沖縄でもない東京近郊の庭。風土が人と物語を作る、それがテーマなのだろう。沖田さんの造った庭は美しかった。
風土でふと思い出したのが、若い頃演じた黒澤明監督『天国と地獄』、犯人役の「夏は暑くて眠れない。冬は寒くて眠れない」というせりふ。あれはハワイでもアラスカでも成立しない。
2017.9.13.記
沖田監督コメント
山﨑努さんが、熊谷守一役をやる主演映画。それを想像するだけで、ワクワクしました。まず僕がそれを観たいと思いました。山﨑さんが小さな蟻をじっと見たり、虫を追いかけたり、そんな楽しそうなシーンを想像しながら、映画を思い描きました。実在した画家である熊谷守一さんのイメージを追いつつ、また、離れつつ。この映画だけの「モリ」という役を山﨑さんと作ることが、どれだけ大変で、楽しかったことか。僕にとっては、夢のような映画です。
熊谷守一(1880-1977年)プロフィール
明治に生まれ、大正・昭和の画壇で活躍した洋画家。美術学校を首席で卒業し、若い頃から絵の才能を認められながらも、いい絵を描いて褒められようとも有名になろうとも思わず、たまに描いた絵も売れず、長いこと借家を転々として友人の援助で生きながらえる。ぽつぽつ絵が売れてようやく家族を養えるようになったのは50歳を過ぎた頃。この頃の有名なエピソードとして、作品を二科展で見た昭和天皇が「これは子どもの絵か」と尋ねたという。やがて、その風貌や言動から「画壇の仙人」としてひろく脚光をあびる。文化勲章と勲三等叙勲を辞退。その理由を「これ以上、人が訪ねて来るのと困るから」と言っていたが、本当は褒状をもらうのが嫌だったため。そうして、家の外へ出ることなく、ひたすら自宅の庭で動植物を観察し続けました。映画は、そんな熊谷守一のエピソードを元に、晩年(94歳)のある1日をフィクションとして描く。
熊谷守一は2017年に没後40年を迎え、12月1日からは東京国立近代美術館にて200点以上の作品を集めた大回顧展が開催。詳細は東京国立近代美術館「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」へ。
『モリのいる場所』
2018年全国公開
監督・脚本:沖田修一 主演:山﨑努
配給:日活
STORY 自宅の庭には草木が生い茂り、たくさんの虫や猫など、守一の描く絵のモデルとなる生き物たちが住み着いている。守一は30年以上、じっとその庭の生命たちを眺めるのを日課にしていた。普段、守一は妻の秀子と二人の生活をしているが、毎日のように来客が訪れる。守一を撮ることに情熱を燃やす若い写真家の藤田くん、看板を書いてもらいたい温泉旅館の主人、隣人の佐伯さん夫婦、郵便屋さんや画商や近所の人々、そして、得体の知れない男・・・
今日もまた、モリとモリを愛する人々の、可笑しくて温かな1日が始まる。
(c)2017「モリのいる場所」製作委員会