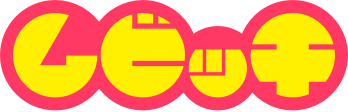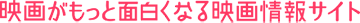ドイツの大ベストセラー小説を、『ソウル・キッチン』『消えた声が、その名を呼ぶ』の名匠ファティ・アキンが実写化した『50年後のボクたちは』が9月16日(土)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国順次公開となる。本作の公開に先立ち、先日9月9日(土)にヤングアダルト文学の先駆者で翻訳家の金原瑞人さん、ドイツ人エッセイスト/コラムニストのマライ・メントラインさん、そしてマライさんの旦那様でドイツ研究者の神島大輔さんを招き、下北沢B&Bで公開記念トークイベントが実施された。
会場には原作本のファンの方を含め、さまざまな世代の方が集まった。原作「14歳、ぼくらの疾走」は、大人も巻き込んで社会現象になった大ベストセラー小説。具体的にドイツでの反応はどうだったのか?マライさんが解説してくれた。「作者のヘルンドルフは自分の死を前にして、今までの人生は何だったのか、残したいものは何かということをいろいろ考えたようです。その気持ちが作品に強く反映されている気がします。作者が闘病中に書いたブログによるとと、脳腫瘍になった直後の4月に書き始めて6月には書き上げています。すごく短期間で『一日一章書くぞ』というスケジュールがあったそう。他の作品ではここまでのヒットにつながらなかったのを見ても、まさにこれを書くために生まれてきたと言ってもよいのではないでしょうか」
このようにヤングアダルト文学が大人にも読まれるのは、ドイツだけに限らない。アメリカやイギリスの文学を数多く翻訳してきた金原さんは語る。「アメリカ、イギリスで大人を対象に「マイベストブック」をアンケートすると、1位は「指輪物語」で「ナルニア国物語」も10位以内に入る。世代を超えてやはり心に残る小説はあるんです。これは日本ではあまりないことです」
さらに、原作の魅力は主人公たちの言葉遣いにもある。「原作からすでに特徴的だったのが、いかにもおじさんが書いたな、と思わせる若者言葉ではない、先々まで古くならない独特の言葉のセンス。上から目線だったり、大人の影を感じるようなものが多いなか、リアルなスラングとは違う独自のスラングを使っているのも魅力的」とマライさんも絶賛!神島さんも「これは翻訳にもつながりますが、日本語の「ナウい」みたいな言葉を使うと後で読んでイタいなと思ってしまいがち、そうではなく先々読んでも古臭く感じない言葉のチョイスがうまいんだと思います」と語った。
原作も映画も共通して、転校生のチックは14歳にもかかわらずお酒を飲み、二日酔いで通学するなどの描写がある。にも関わらず、ドイツでは原作が推薦図書となり学校の勉強の教材となっている。マライさんは「ドイツではよくあることだけど、大ヒットした小説は学校の授業にも取り込まれる。ドイツでは小学4年から宿題で本を読んできて、内容についてディスカッションする授業があります。原作もそのような動きがあったようです」と語る。神島さんは「文部省推薦のような児童書は日本だと、現実社会のダークな部分を書かず、書いていたら選定から外れてしまう。でもドイツでは現実を直視するほうが正しいとされていて、だからこそ教材になるんではないでしょうか。またドイツでは学校でこの本をテーマにさらに議論をする。これも日本の学校と大きく違いますね」
金原さんは「アメリカの60~70年代は社会的に揺れた時代。離婚率も増えて、ウーマンリブ、黒人の公民権運動などが起きます。その陰で、少年の非行、セックス、ドラッグなど子どもたちにもさまざまな問題が出てきます。この時代から、児童文学の作家も、未来への希望ばかり書いてきたのではなく直面している現実の問題をリアルに書くという動きが出てきます。これがヤングアダルト文学の生まれと言われています。「14歳、ぼくらの疾走」も、まさにそういった社会的要素を取り入れているなと思います」と解説してくれた。
これまで数多く作られてきたロードムービーと比べ、本作『50年後のボクたちは』の持つ魅力について神島さんは、「子どもの冒険ものの王道と言ったら名作『スタンド・バイ・ミー』ですよね。これは子どもたちが死体探しに行くという、目的をもって冒険する。でも『50年後のボクたちは』はそうではなく、目的が曖昧なまま出発してしまうという面白さ。あとは、『スタンド・バイ・ミー』は現実社会の累計に対する、大人が押し付ける子どもへの価値観の押し付けに対する闘いがあります。それと比べて今回の映画は、非常に捉えどころがないところが多い。複雑化している今をうまく表現していて、時代性の違いというのがよく出ているのではないでしょうか。あと映画では、旅に出ているシーンはもちろんなのですが、旅に出て帰ってきてからの展開が素晴らしくてとっても味わい深いものになっている」と分析した。
マライさんは「ドイツのどの監督も映画化を熱望していて、当初は違う監督がやる予定だったのが、最終的にファティ・アキンにまわってきたそう。監督も原作に相当思い入れがあり、用意されていた脚本も書き直し役者も自分でキャスティングし直したほど(当初は18歳の役者が演じる予定だった)。ファティ・アキンは社会の問題提示をテーマに、時に暴力的な描写もする監督のイメージだったので『どうなるんだろう…』と思っていたら、できたものが本当に素晴らしくて国内でもとても評価が高かったです。映画は主人公マイクの視点で描かれているのですが、14歳特有の子どもらしい楽観的な面と、意外に大人な視点を持ち合わせている。その微妙な部分を見事に描写しているんですよね。クスっと笑いながらもグッときてしまいました」と語った。
そして、3人とも声を揃えてお気に入りのシーンと答えたのは、マイクとチックが風力発電所の下で野宿をするシーン。夜空を見上げて2人で語り合う印象的な場面だ。金原さんは「ここのダイアローグは、何度観ても泣けるシーン。ここを観るだけでも映画を観る価値がある!」と太鼓判を押した。
今の日本では、ヤングアダルト文学よりライトノベル小説のほうが、若者たちから親しまれているのが現状。アニメやゲーム業界にも詳しい神島さんは語る。「ここ1~2年の話ですが、最近のライトノベル小説の書き手たちの登竜門で「小説家になろう」というサイトがあって、そこから発した言葉で「なろう系」という言葉がある。数年前までは定番の学園ものでも、そこに葛藤があっていかに克服していくかということが流れとして受け入れられてきた。しかし今は、主人公が努力をせずに結果を得る。要は異世界に主人公が飛ばされて自分の持っているスキルが生かされて労せずに結果を得るということ。それが受け入れられるのは、若者が未来に希望がなく、努力で結果を得られるというのは幻想だと思っているということ。そういった市場で一体どういった作品を作ればよいかという声があります。努力や成長を拒絶するというのは、本来のヤングアダルトから真っ向から対峙していますよね」
「この作品はうまくはまっている気がする。建前的な偽善を排したかたちで、でも人間は成長するんだというベクトルを指していることに成功しているのではないでしょうか。あとは映画の細かいところで言うと、マイクとチックが遊ぶゲームが『スーパーマリオ』のような牧歌的なものでなく、暴力的なシューティングゲームで、でもかといって彼らは暴力的でない。ここに彼らがなんとなく蓄積しているストレスが感じられる。あとは中途半端に何でも知っている感覚は、ネット社会で育つ子ども特有な点だったりと、すごくリアルな若者像がここにあると思います」と神島さんは続ける。
最後に会場に駆け付けた映画をこれから観る人たちへ向けて、金原さんは「こういう映画は無理に親子で行く必要はなく、子どもは大人に隠れ、親も子どもに隠れてこっそり見る。それが正しい(笑)。この映画は、まさにヤングアダルトの本質といえる映画だと思います!」と語った。
マライさんは「とにかく映画も原作も大好き!ドイツというとナチスものが多いなか、久々にこういう映画が出てきて嬉しいです。原作のヘルンドルフの人生感が強く出ていて、決して古くならない作品。まさに「人間おすすめ映画」だと思います!」と語った。
そして神島さんは「ドイツが移民問題に揺れる中、ファティ・アキンもトルコ系ドイツ人ということで、移民パワーが強い力を発揮しているんだなと思いました。ドイツを内からでなく、少し外からの視線で描くことが、新たな面白さを発見できます。またいまの複雑化した世界で、「啓蒙」とは果たして可能なのか?そういう観点からも、ぜひ観て共有したい作品です」と締めくくった。
『50年後のボクたちは』
9月16日(土)より、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国順次ロードショー
監督・共同脚本:ファティ・アキン
原作:ヴォルフガング・ヘルンドルフ(「14歳、ぼくらの疾走」)
出演:トリスタン・ゲーベル アナンド・バトビレグ・チョローンバーダル
配給:ビターズ・エンド
STORY 14歳のマイクはクラスのはみだし者。同級生からは変人(=サイコ)扱い、両親の仲もうまくいっていない。そんなある日、チックというちょっと風変わりな転校生がやって来た。夏休み、2人は無断で借用したオンボロ車ラーダ・ニーヴァに乗って南へと走り出す。旅の途中で訪れる、いくつもの出会いと別れ。やがて無鉄砲で考えなしの旅は、マイクとチックにとって一生忘れることのできないものになっていく――。
©2016 Lago Film GmbH. Studiocanal Film GmbH